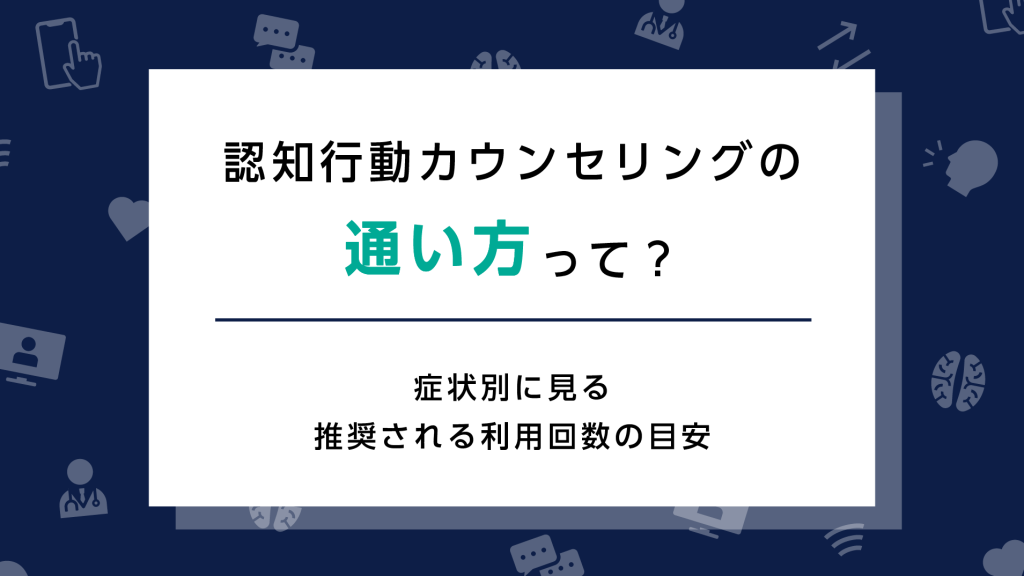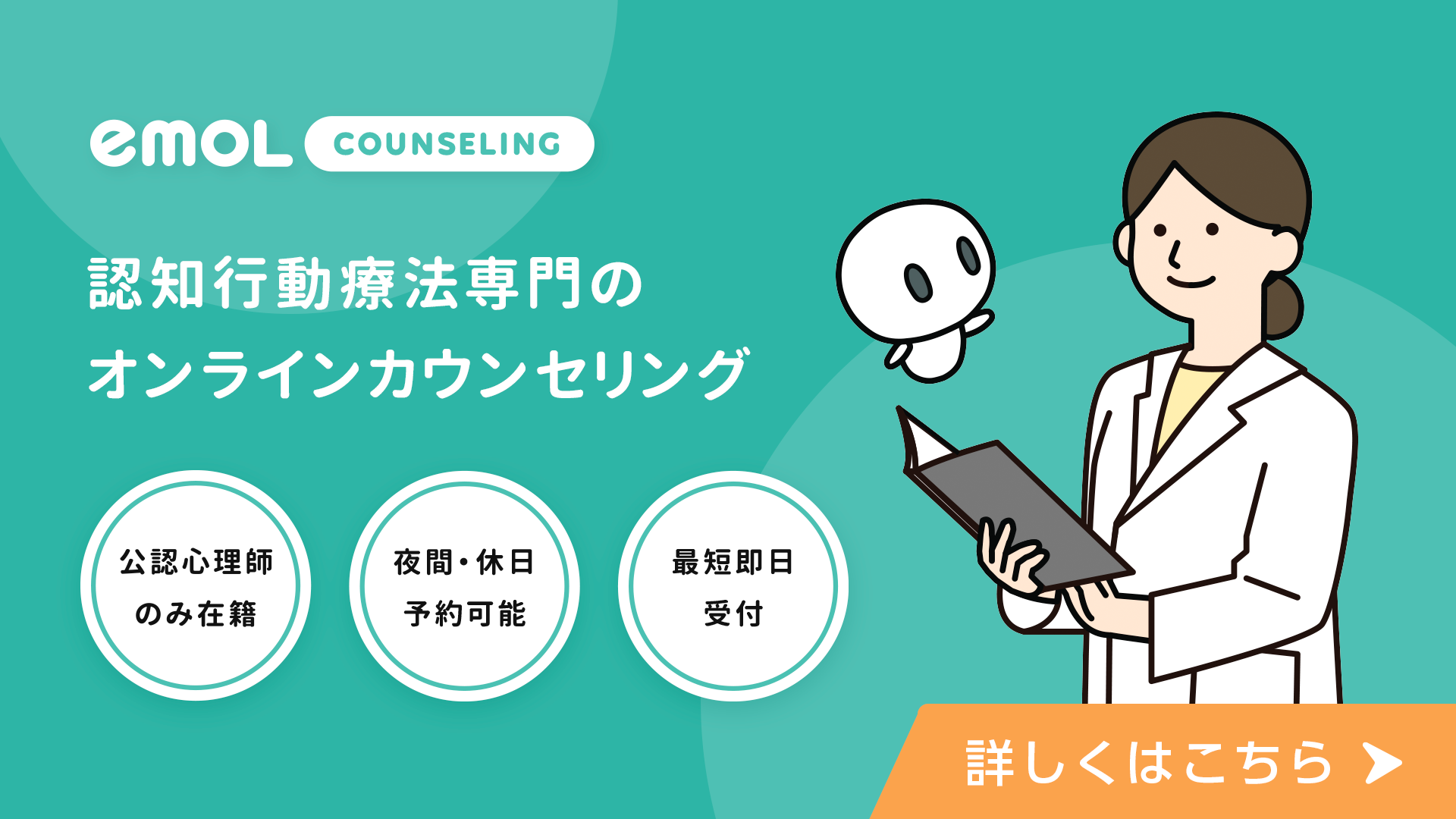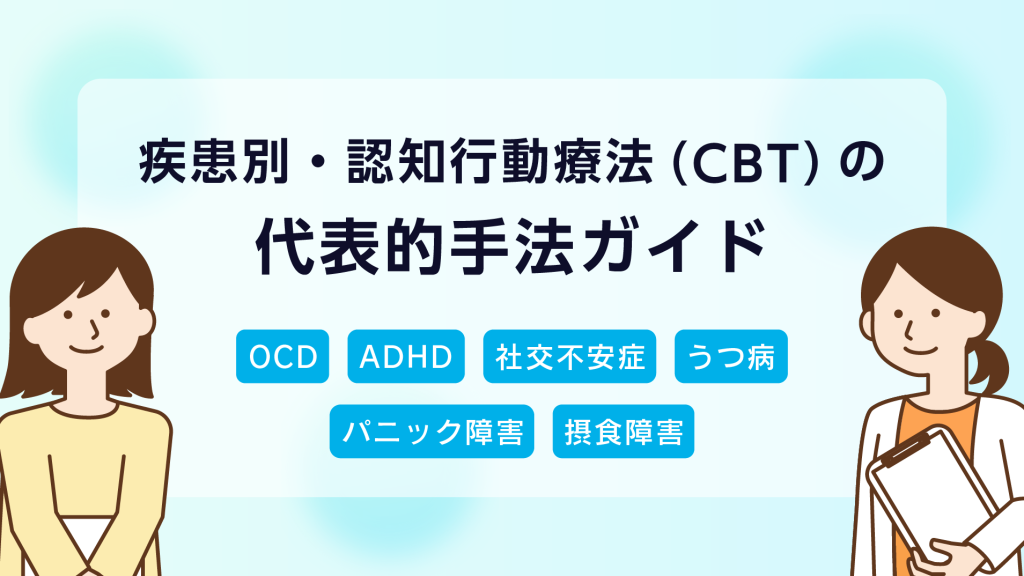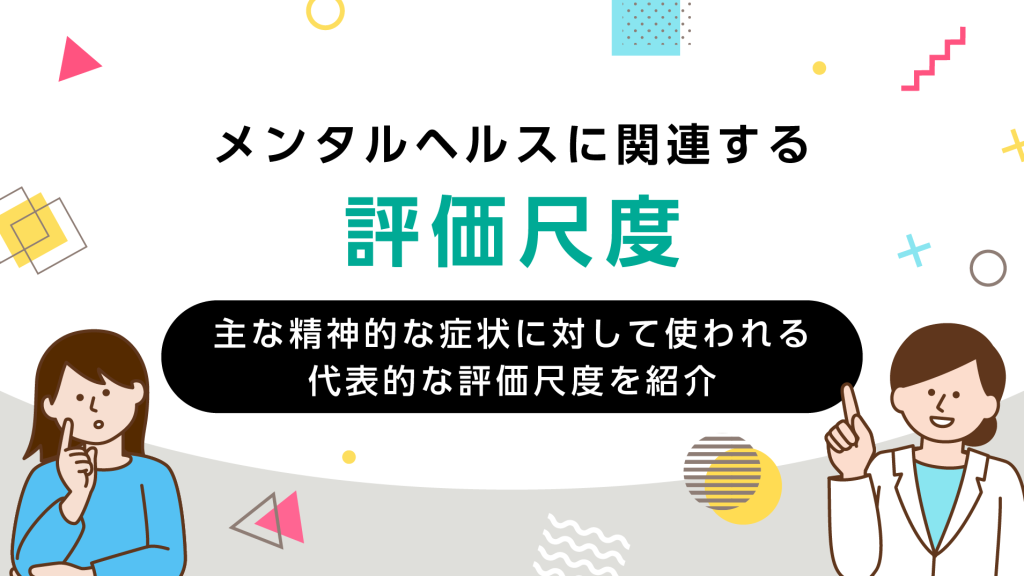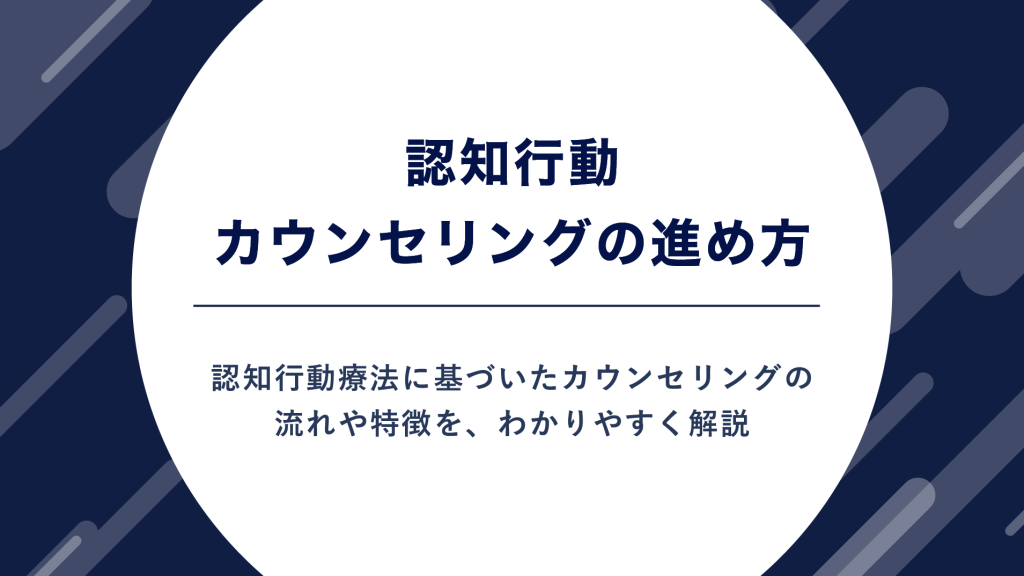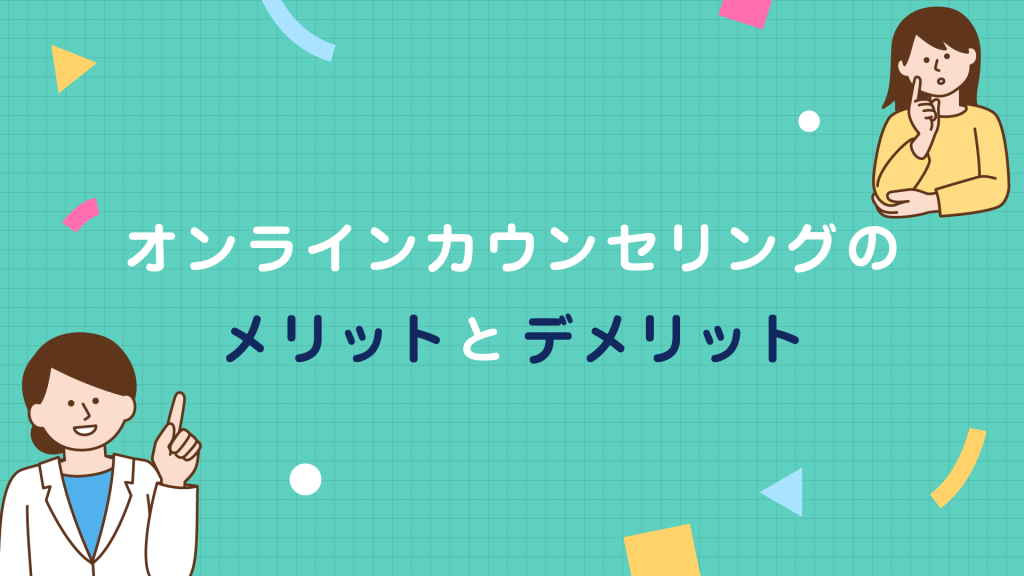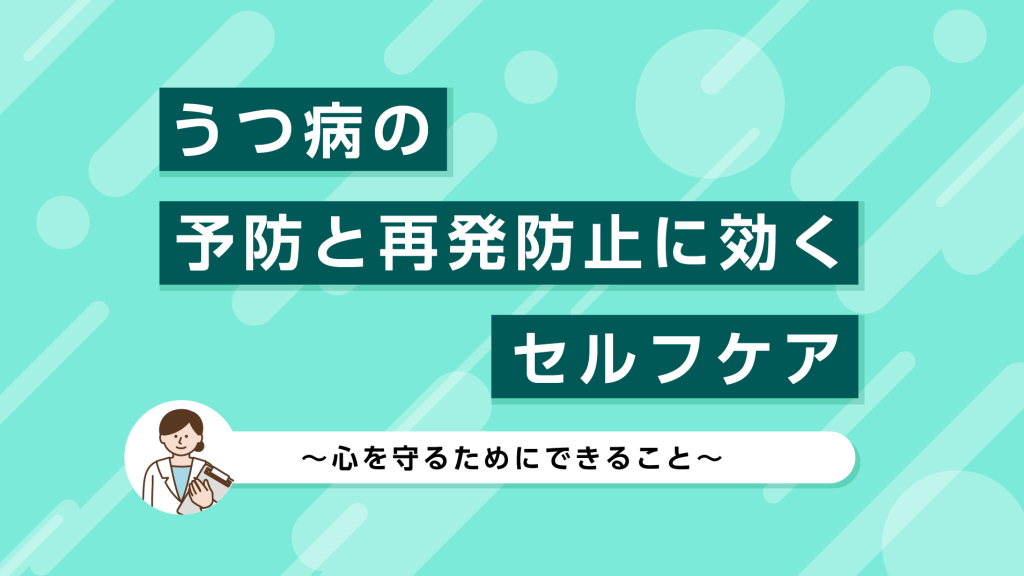心の不調を感じたとき、カウンセリングを受けてみようと思っても「どれくらい通えば効果があるの?」「症状によって回数は違うの?」といった疑問がわく方も多いのではないでしょうか。
この記事では、認知行動療法(以下CBT)で推奨されているカウンセリング回数の目安を、代表的な心の状態や症状ごとにご紹介します。あくまで「目安」であり、個人の状態によって適切な頻度や期間は異なります。主治医やカウンセラー(臨床心理士/公認心理師など)と相談しながら、無理なく取り入れてみてください。
目次
認知行動療法(CBT)とは?
認知行動療法(CBT)とは、「考え方」や「行動」のクセに働きかけることで、ストレスや不安、落ち込みなどの心の不調を和らげることを目指す心理療法です。
症状を「変えよう」とするのではなく、考え方や行動の幅を広げて、より自分らしく生きる力を育むアプローチです。
薬物治療との併用や、再発予防の手段としても活用され、科学的根拠に基づいた心理療法として注目されています。
症状別:カウンセリング回数の目安
1. うつ病(大うつ病)
推奨回数の目安:16〜20回程度
うつ病に対するCBTでは、週1回ペースで3〜4か月継続することが多く、16回前後が1クールの目安とされています。初期は行動活性化(少しずつ行動を増やすことで心の元気を取り戻す方法)を中心に行い、次第に考え方や行動のクセにも働きかけていきます。
2. 強迫症(強迫性障害/OCD)
推奨回数の目安:16回
「手を何度も洗ってしまう」「確認行為がやめられない」などの強迫性障害では、曝露反応妨害法という行動療法が中心になります。段階的に不安に慣れていく方法で、安全に進めるために回数は多めに設定されることが一般的です。
3. 社交不安症(社交不安障害/SAD)
推奨回数の目安:12〜16回
人前で話すのが怖い、人と接することが苦手……という社交不安障害には、「自分の思い込み」に気づく練習や、実際の場面での対処行動を一緒に考えることが重視されます。
セッションの中では、「安全な練習の場」をつくることも多いため、一定の回数を要します。
4. パニック症(パニック障害)
推奨回数の目安:21回
突然の動悸や息苦しさに襲われるパニック発作に対するCBTでは、「不安を感じる場面」に少しずつ慣れていく練習(曝露療法)と、「不安を大きくしすぎてしまう思考パターン」の見直しを行います。
継続的に取り組むことで、安心できる行動パターンを増やしていくことが期待されます。
回数は「目安」。自分のペースを大切に
CBTは具体的な目標に向かって進めやすいカウンセリング方法として、さまざまな心の不調に対応しています。上記の回数は、あくまでも一般的な目安です。回数に正解はなく、症状の程度や生活環境、過去の経験などによって、必要な回数は人それぞれ異なります。また、「一度きりの相談」でも、自分の考えを整理できたり、気づきが得られることもあります。
大切なのは、無理のないペースで自分の心に向き合えることです。カウンセラーと一緒に、取り組み方を調整していきましょう。
※本記事は医療行為を目的としたものではありません。心の不調が続く場合は、医師や専門家にご相談ください。
emolのオンラインカウンセリング
emolのオンラインカウンセリングは、認知行動療法に特化してオンラインのカウンセリングを提供しています。臨床心理士・公認心理師のみが在籍し、認知行動カウンセリングの経験豊富な専門家が担当いたします。心のケアを始める第一歩として、ぜひ一度お試しください。

参考文献一覧
- 「うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料) 」厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業 「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」
- 「強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用)」厚生労働省
- 「社交不安障害(社交不安症)の 認知行動療法マニュアル (治療者用)」厚生労働省
- 「パニック障害(パニック症)の 認知行動療法マニュアル (治療者用)」厚生労働省