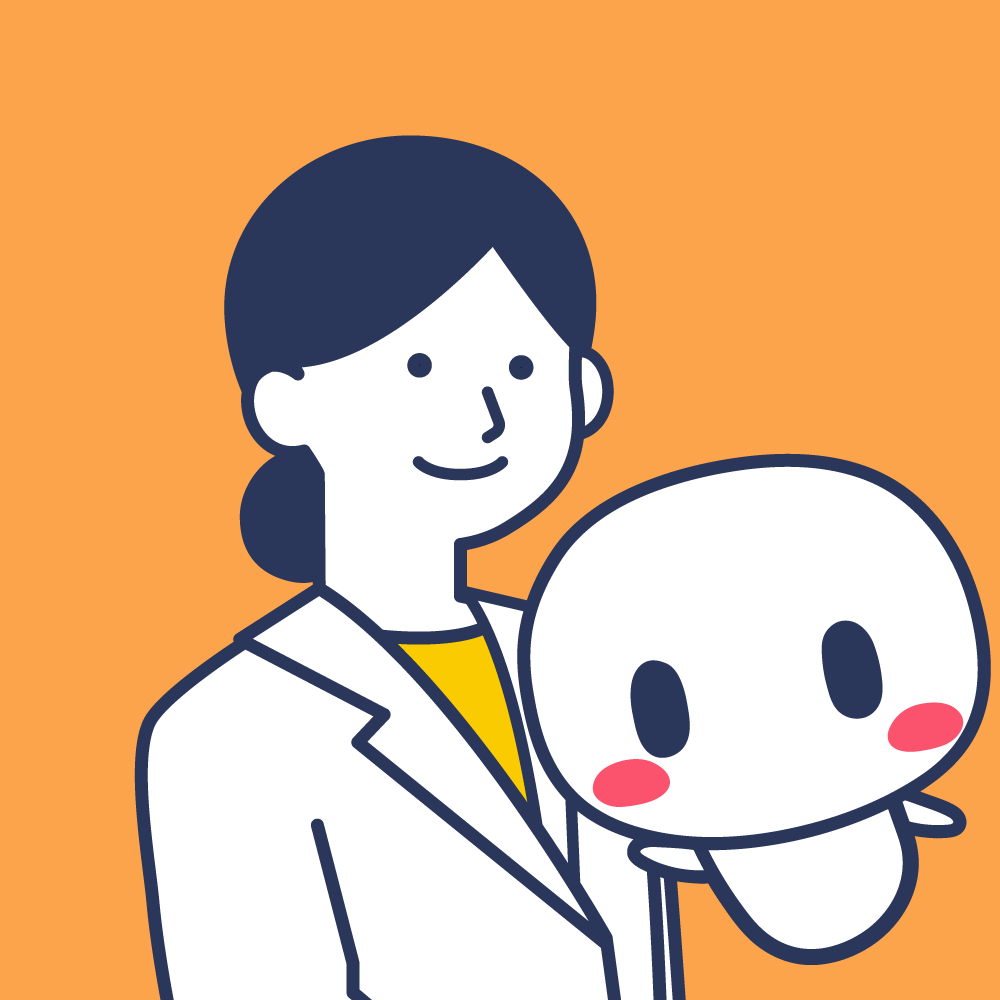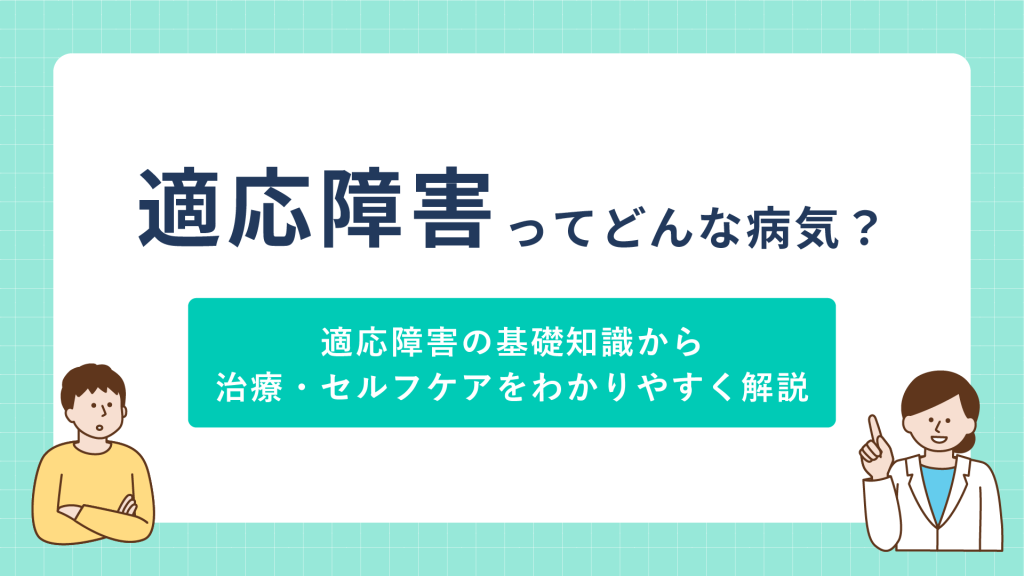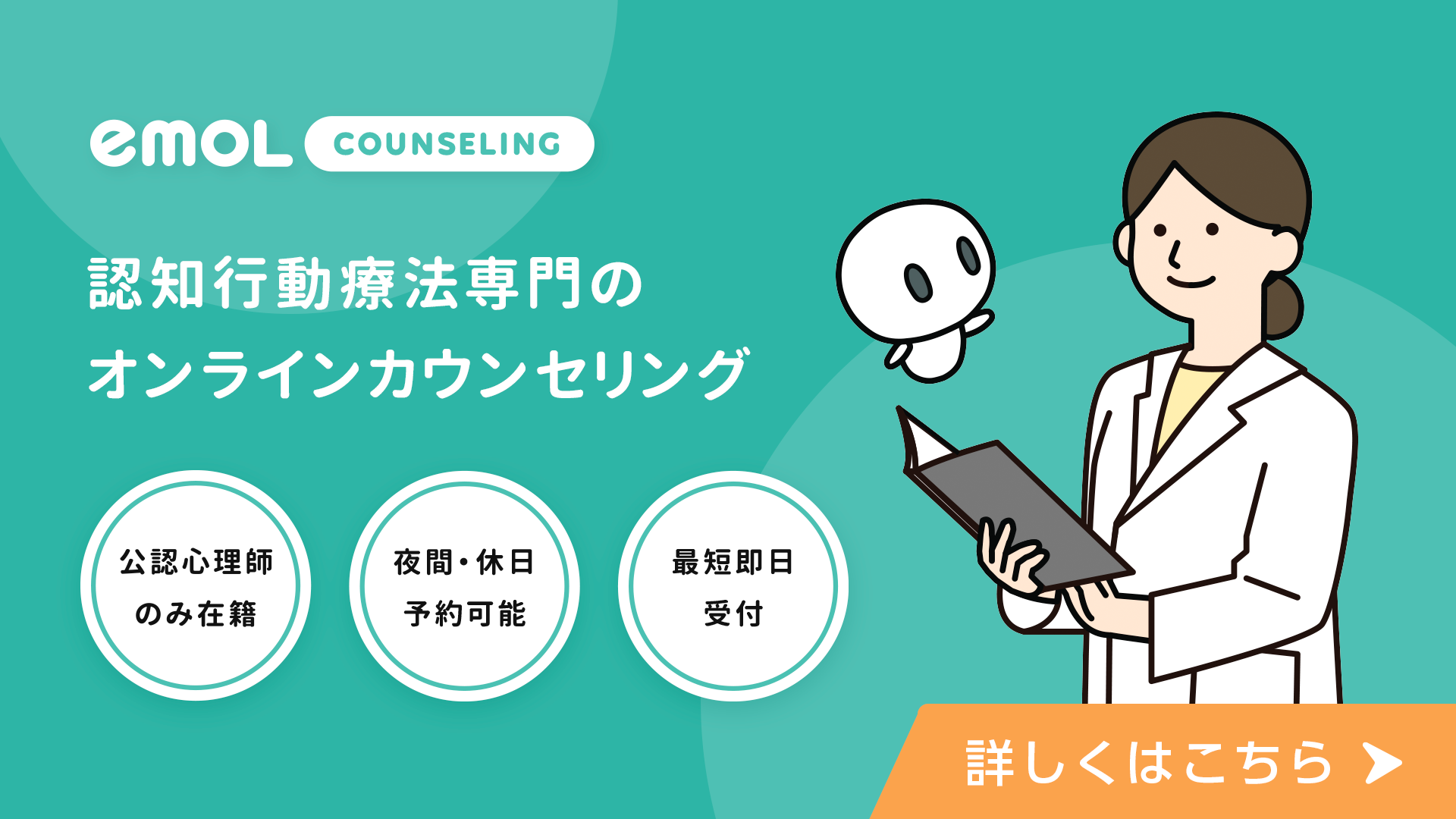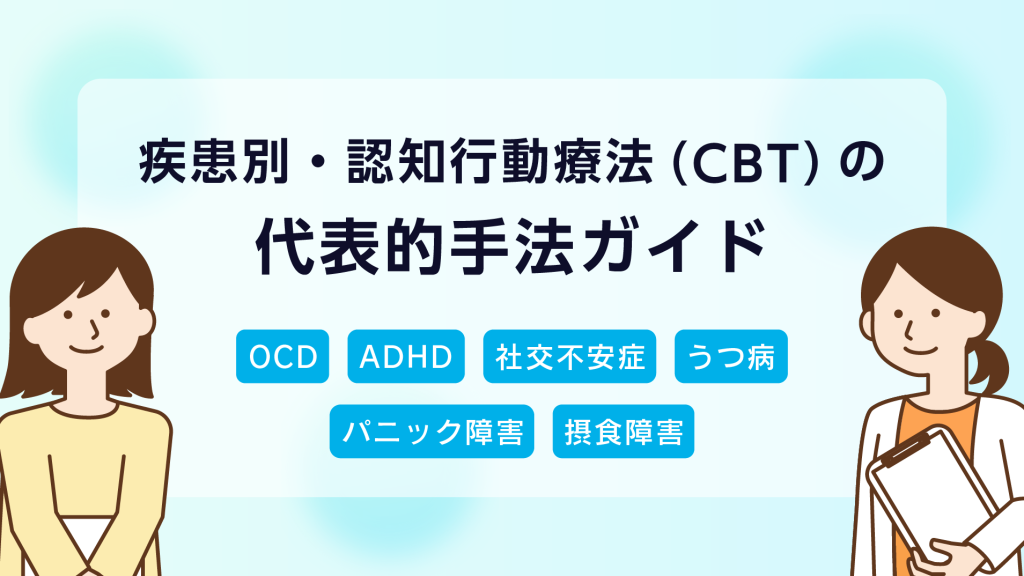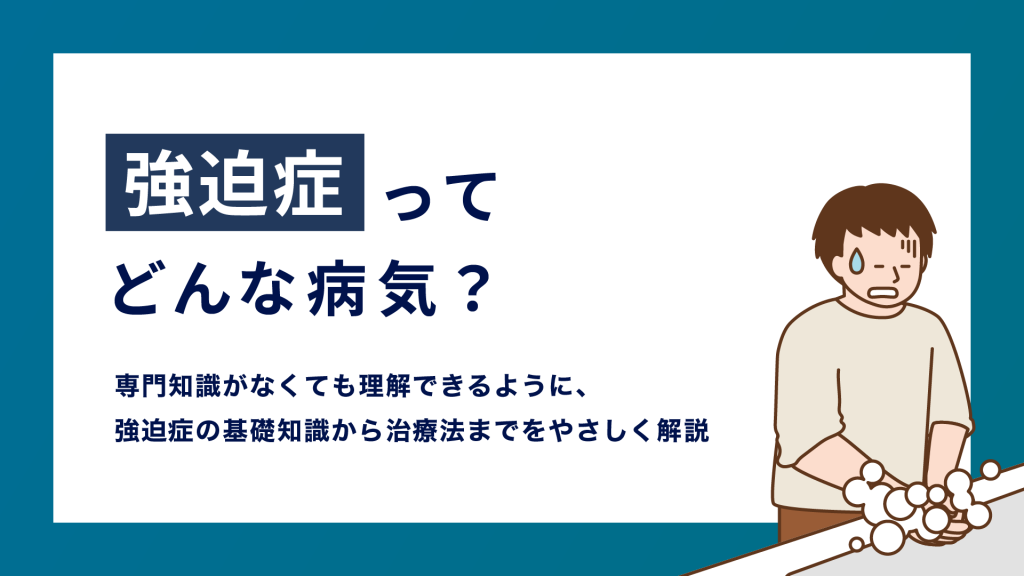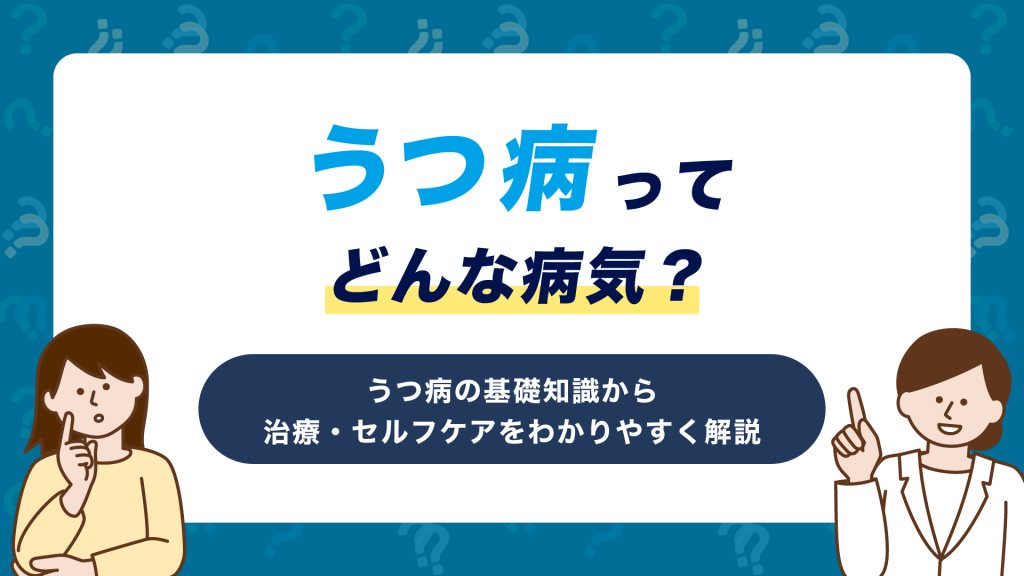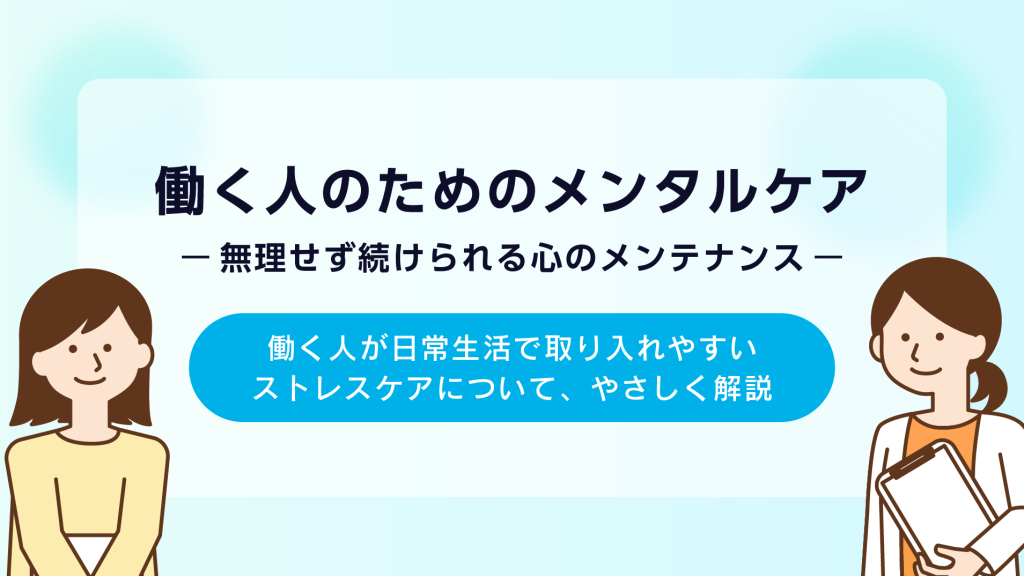「適応障害」という言葉を聞いたことがありますか?
最近ではニュースやドラマでも取り上げられるようになり、少しずつ知られるようになってきました。しかし、実際にどんな病気なのか、うつ病との違いは何かを理解している人はまだ多くありません。
適応障害は強いストレスが原因となって心や体に不調が現れる病気です。早めに対処すれば回復しやすい一方、放っておくとうつ病などに進展することもあります。
この記事では、適応障害の原因・症状・診断基準・治療法について、専門知識がない方でもわかりやすく解説します。
目次
適応障害とは?
適応障害とは、生活の中で大きなストレスを受け、その状況にうまく適応できずに心身の不調が出る状態を指します。
たとえば、以下のような状況がきっかけになることがあります。
- 職場での人間関係のトラブル
- 転職や部署異動などの環境変化
- 学校生活や受験のプレッシャー
- 家族関係の問題、介護、離婚
- 災害や事故などの出来事
こうしたストレスに対して通常の範囲を超えて強く反応し、気分の落ち込み・不安・体調不良などが生活に支障を与える状態が適応障害です。
適応障害の症状
適応障害の症状は人によって異なりますが、大きく分けて「心の症状」「体の症状」「行動の変化」の3つがあります。
心の症状
- 気分の落ち込みが強い
- 不安や焦りが続く
- イライラしやすい
- 集中力の低下
- 将来に対する悲観的な思考
体の症状
- 不眠(寝つけない、眠りが浅い)
- 食欲不振や過食
- 頭痛、腹痛、倦怠感
- 動悸や息苦しさ
行動の変化
- 遅刻や欠勤が増える
- 学校や仕事に行けなくなる
- 趣味や日常の活動に興味を失う
- 衝動的な行動(暴言、過度の飲酒など)
これらの症状はストレス要因が続いている間に起こりやすいという特徴があります。
適応障害の診断基準
適応障害は、米国精神医学会の診断基準(DSM-5)に基づいて診断されます。主な基準は以下の通りです。
- 明確なストレス要因があり、その出来事から3か月以内に症状が出ている
- 社会的・職業的な機能(仕事・学業・家庭生活など)が著しく低下している
- 他の精神疾患(うつ病や不安障害など)では説明できない
つまり、ストレス要因が明確であり、その影響によって生活に支障が出ているかどうかが診断のポイントです。
適応障害とストレス反応のちがい
誰でもストレスを受ければ気分が沈んだり、眠れなくなったりします。
しかし通常は時間の経過とともに落ち着いていきます。
一方で適応障害は、
- 不調が長く続く(数週間以上)
- 学校や仕事に行けない、家事ができないなど生活に支障が出る
- 気持ちを切り替えられず、悪循環が続く
といった特徴があります。
適応障害とうつ病の違い
よく混同されるのが「うつ病」との違いです。
■適応障害
→ 明確なストレス要因があり、その状況に反応して症状が出る。ストレス要因がなくなると症状は改善することが多い。
■うつ病
→ 特定のストレス要因がなくても発症する。脳の機能異常が関与し、長期化しやすい。
適応障害は「環境に対する反応」として現れるのに対し、うつ病は「病気そのもの」として存在するという点が大きな違いです。
適応障害の治療法
適応障害は、ストレス要因を軽減し、心身のバランスを取り戻すことが基本です。
① 環境調整
職場の部署変更や業務量の見直し、学校での配慮など、ストレス要因を減らす工夫を行います。
② 薬物療法
症状が強い場合は、抗不安薬や睡眠薬、場合によっては抗うつ薬が用いられることもあります。
③ 精神療法(カウンセリング)
認知行動療法(CBT)や支持的カウンセリングが効果的です。
「考え方の癖」に気づき、ストレスへの対処法を学ぶことが再発予防につながります。
④ 休養
一時的に仕事や学校を休み、心と体を休ませることが必要になる場合もあります。
適応障害になりやすい人の特徴
- 責任感が強く真面目
- 完璧主義
- 人に頼るのが苦手
- 環境の変化に弱い
ただし、誰でも強いストレスを受ければ発症する可能性があります。「自分が弱いから」ではなく、誰にでも起こり得る病気です。
適応障害の予防とセルフケア
- 悩みを一人で抱え込まず、人に相談する
- 趣味や運動などでリフレッシュする
- 睡眠と食生活を整える
- ストレスを感じたら早めに休む
セルフケアで改善が難しいときは、早めに専門家へ相談することが大切です。
まとめ
適応障害は、強いストレスがきっかけで心や体に不調が出る病気です。
ストレス要因が明確であること、環境を調整すれば改善しやすいことが特徴です。
治療には「環境調整」「薬物療法」「カウンセリング」「休養」があり、早期に対処すれば回復しやすい病気です。
「気分の落ち込みが続いている」「仕事や学校に行けないほどつらい」という場合は、我慢せずに専門家へ相談してみましょう。
参考文献一覧
- 厚生労働省. 「みんなのメンタルヘルス総合サイト 適応障害」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/info_03.html - 国立精神・神経医療研究センター. 「適応障害」疾患ナビゲーション
https://www.ncnp.go.jp/nimh/clinical/adaptation/ - 日本精神神経学会. 精神疾患の診断・統計マニュアル DSM-5
American Psychiatric Association, 2013. - Mayo Clinic. “Adjustment disorders.”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/adjustment-disorders/ - 世界保健機関(WHO). International Classification of Diseases (ICD-11).