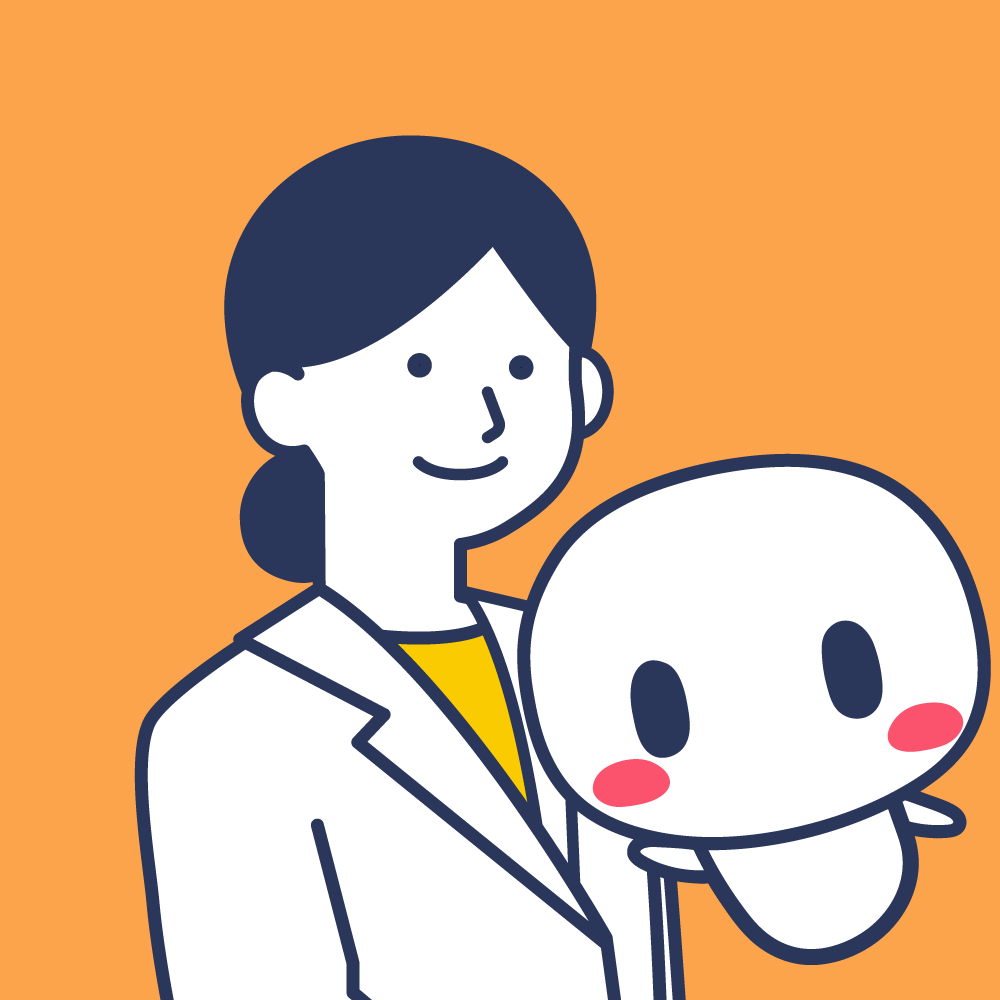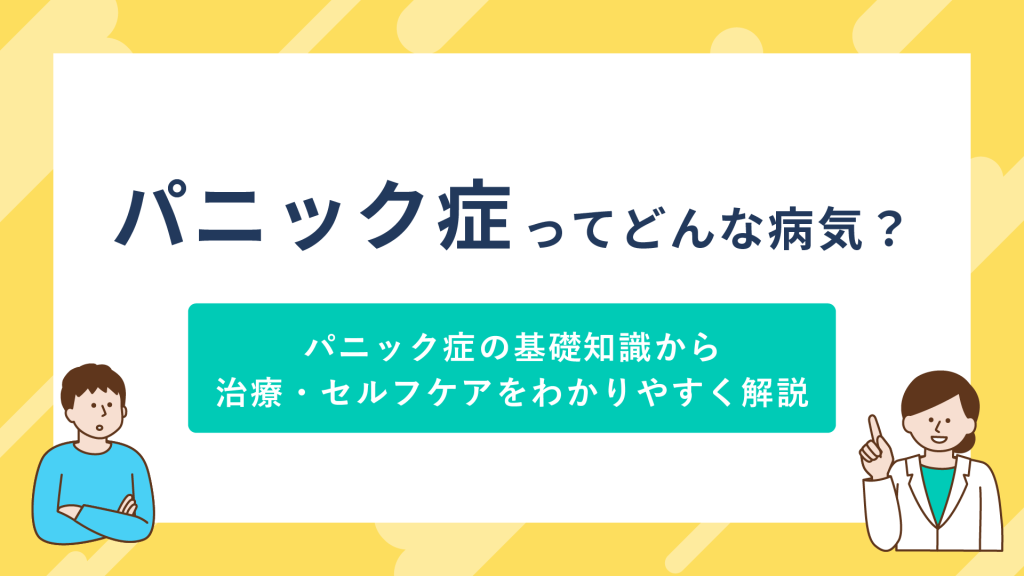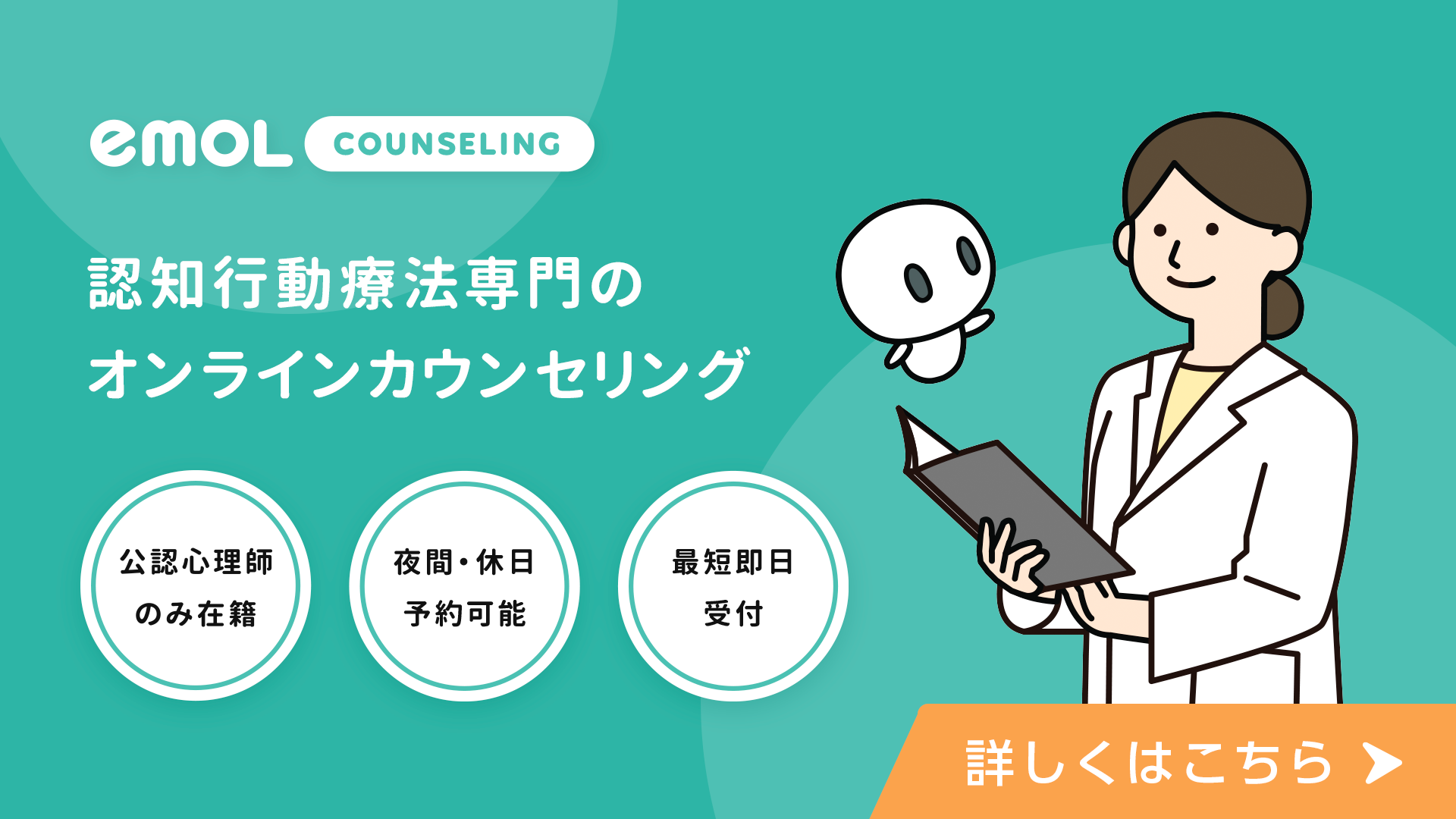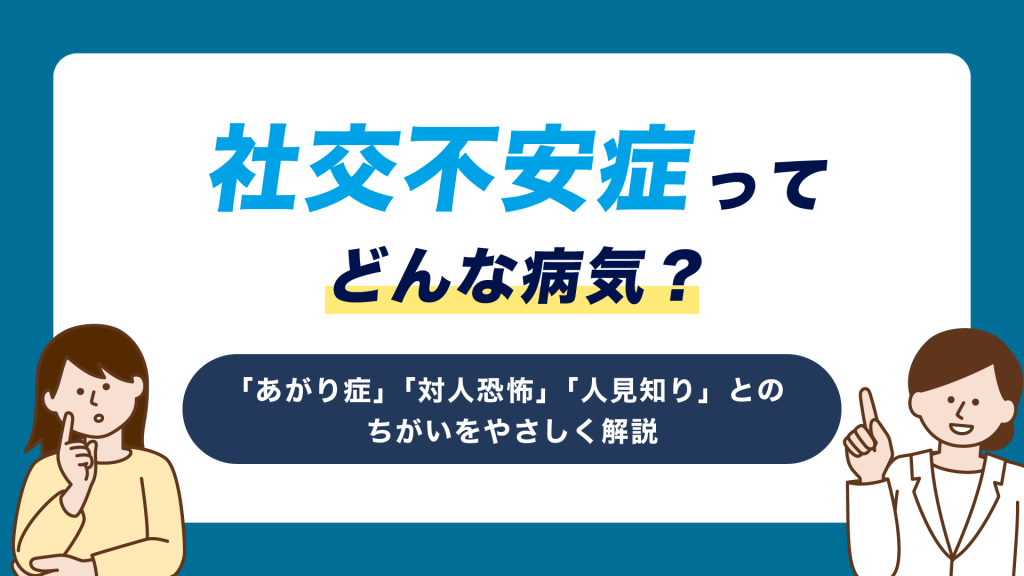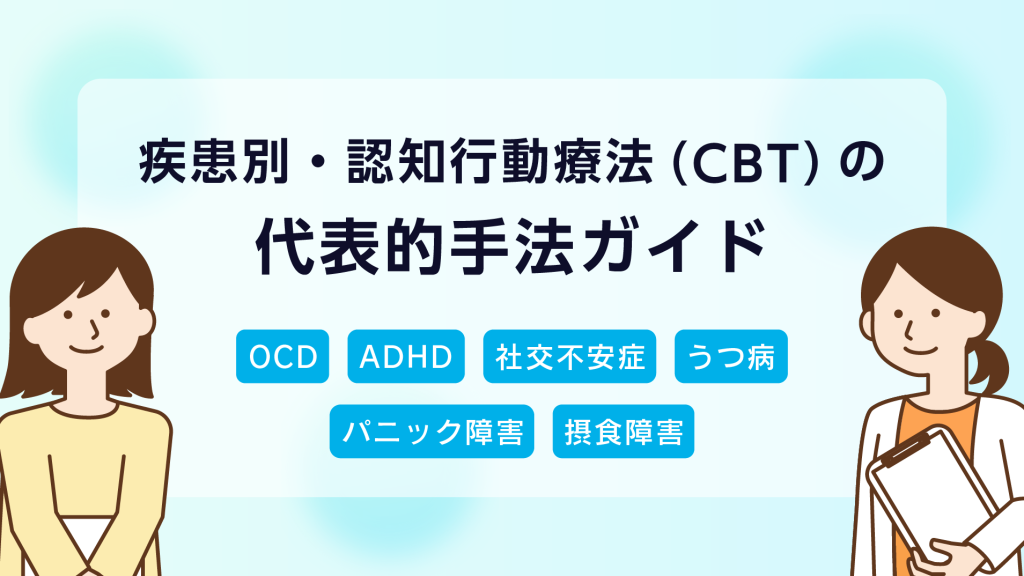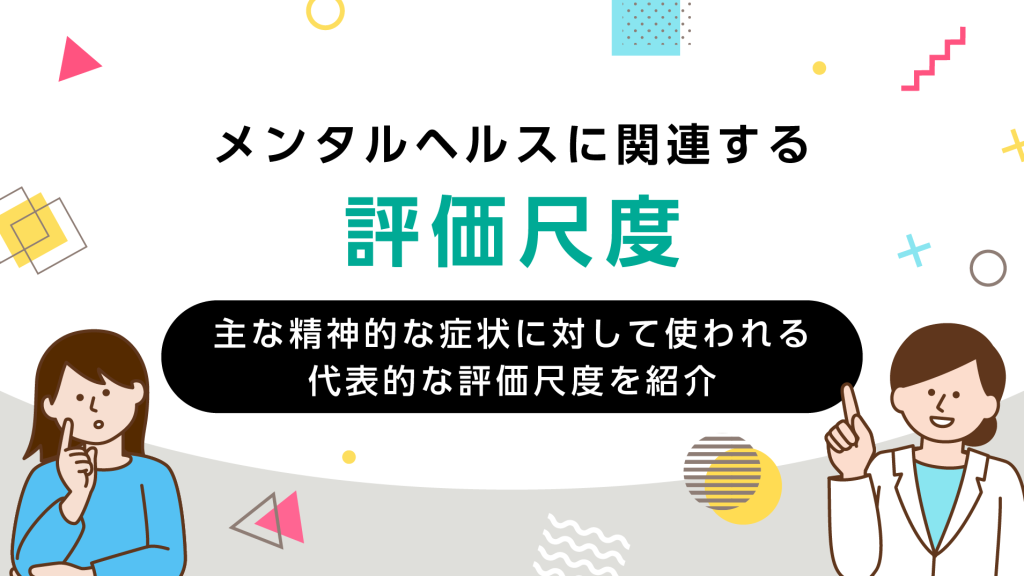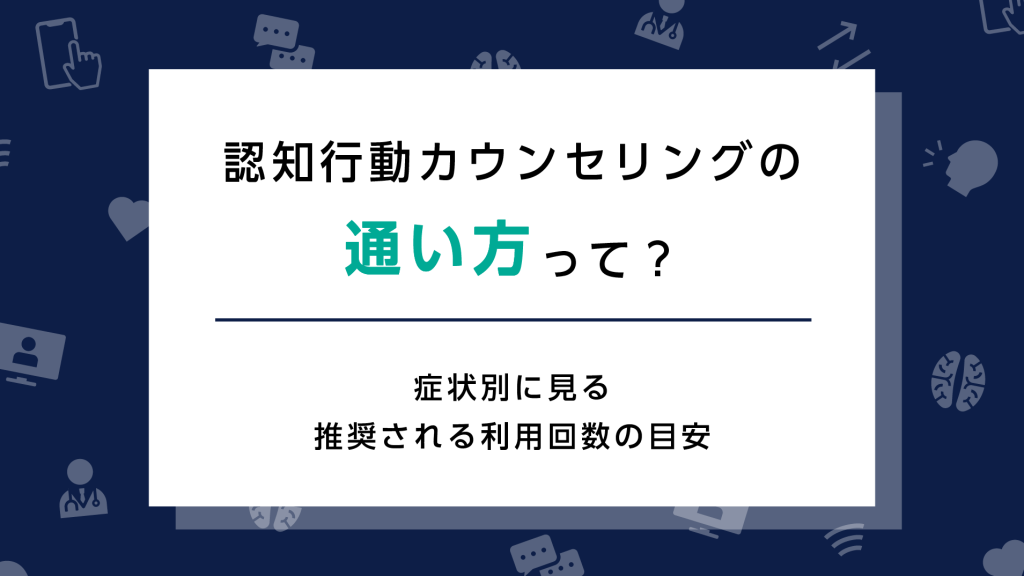目次
はじめに
突然、強い動悸や息苦しさ、めまいが襲ってきて「このまま死んでしまうのではないか」と感じる。
それが繰り返し起こるのがパニック症(パニック障害)です。
最近では芸能人や著名人が公表したことで知られるようになりましたが、実際の症状や治療法については誤解も多くあります。
この記事では、パニック症の症状・原因・治療法・日常生活の工夫について、特別な知識がない方でも理解できるようにまとめました。
パニック症とは?
パニック症とは、予期せぬパニック発作を繰り返し経験し、それに強い不安や恐怖を感じる病気です。
パニック発作とは?
突然、強い身体的・精神的な症状が出て「このまま命を落とすのでは」と思うほどの強烈な不安に襲われる状態です。
主な症状は次の通りです。
- 動悸・胸の痛み
- 息苦しさ、過呼吸
- めまい、ふらつき
- 発汗、震え
- 胃のむかつき
- 現実感が薄れる感覚(離人感)
- 「このまま死んでしまうのでは」という強い恐怖
発作は数分〜30分程度で治まることが多いですが、経験した本人にとっては非常に強烈で、再び発作が起きるのではないかという予期不安が生活を制限してしまいます。
パニック発作とパニック症の違い
まず大切なのは、「一度のパニック発作」と「パニック症」は異なるということです。
単発のパニック発作
過度のストレスや体調不良、睡眠不足、カフェインの摂りすぎなどで一時的に発作が起きることがあります。誰にでも起こり得るもので、必ずしも病気ではありません。
パニック症(パニック障害)
発作が繰り返し起こり、少なくとも1か月以上「また発作が起きるのでは」という強い不安(予期不安)や回避行動が続く状態を指します。日常生活や仕事、人間関係に影響するほどになると診断の対象になります。
パニック症の症状
1. 突然のパニック発作
典型的なのは、何の前触れもなく起こる発作です。心臓発作や窒息と勘違いして救急外来を受診するケースも少なくありません。
2. 予期不安
「また発作が起きたらどうしよう」という強い不安が続き、外出や人前に出ることを避けるようになります。
3. 回避行動
電車や車、映画館、会議室など「逃げにくい場所」を避けるようになり、生活の幅がどんどん狭くなることがあります。
パニック症の原因
パニック症の原因は一つではなく、脳の働きやストレス要因、性格傾向などが複雑に関係していると考えられています。
- 脳の神経伝達物質の異常
→ セロトニンやノルアドレナリンの働きが乱れることで、不安が過敏に生じる。 - ストレス
→ 過労や人間関係の悩み、生活の変化などが引き金になることが多い。 - 性格的要因
→ 真面目、責任感が強い、完璧主義などの傾向がある人に多い。 - 遺伝的要因
→ 家族に不安障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高いとされる。
パニック症の診断
診断は主に問診を中心に行われます。DSM-5(米国精神医学会の診断基準)によると、以下の条件が目安になります。
- 繰り返し予期せぬパニック発作が起きる
- 少なくとも1か月以上、予期不安や回避行動が続いている
- 他の病気(心臓病、甲状腺疾患など)では説明できない
医師は、心電図や血液検査を行い、身体的な病気が原因ではないかを確認したうえで診断します。
パニック症の治療法
① 薬物療法
抗うつ薬(SSRI、SNRIなど)がよく用いられます。不安の過敏さを抑える働きがあり、発作や予期不安を減らす効果があります。
また、急性の発作時には抗不安薬が短期間処方されることもあります。
② 認知行動療法(CBT)
「発作が起きても死ぬことはない」ということを理解し、発作に対する過剰な恐怖を和らげる心理療法です。
呼吸法やリラクゼーション法などを学ぶこともあり、薬物療法と並んで効果が高いとされています。
③ 生活習慣の改善
- 睡眠を十分にとる
- カフェインやアルコールを控える
- 適度な運動(ウォーキングやストレッチ)
- バランスのとれた食生活
④ 家族や周囲の理解
パニック症は本人の努力不足ではありません。周囲が正しく理解し、安心して生活できる環境を整えることも治療の一部です。
パニック症と合併しやすい病気
- うつ病
- 広場恐怖症(人混みや電車などを避ける)
- 社交不安障害
パニック症を放置すると、これらの病気に進展する可能性があるため、早めの受診が大切です。
パニック症のセルフケア
治療と並行して、自分でできる工夫も役立ちます。
- 発作が来ても「必ず治まる」と言い聞かせる
- ゆっくり呼吸する(4秒吸って、4秒吐く)
- 発作の記録をつけ、自分の傾向を知る
- 信頼できる人に気持ちを話す
まとめ
パニック症は、突然の発作が繰り返し起こり、生活を大きく制限してしまう病気です。
しかし、薬物療法や認知行動療法によって改善が可能であり、早期に治療を始めれば生活を取り戻すことができます。
「また発作が起きるのでは」と一人で不安を抱えるのではなく、精神科や心療内科に相談することが第一歩です。
参考文献一覧
- 厚生労働省. 「みんなのメンタルヘルス総合サイト パニック障害」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/info_04.html - 国立精神・神経医療研究センター. 「パニック障害」疾患ナビゲーション
https://www.ncnp.go.jp/nimh/clinical/panic/ - 日本うつ病学会. 「不安障害の診断・治療ガイドライン」
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). 2013.
- Mayo Clinic. “Panic attacks and panic disorder.”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/panic-attacks/