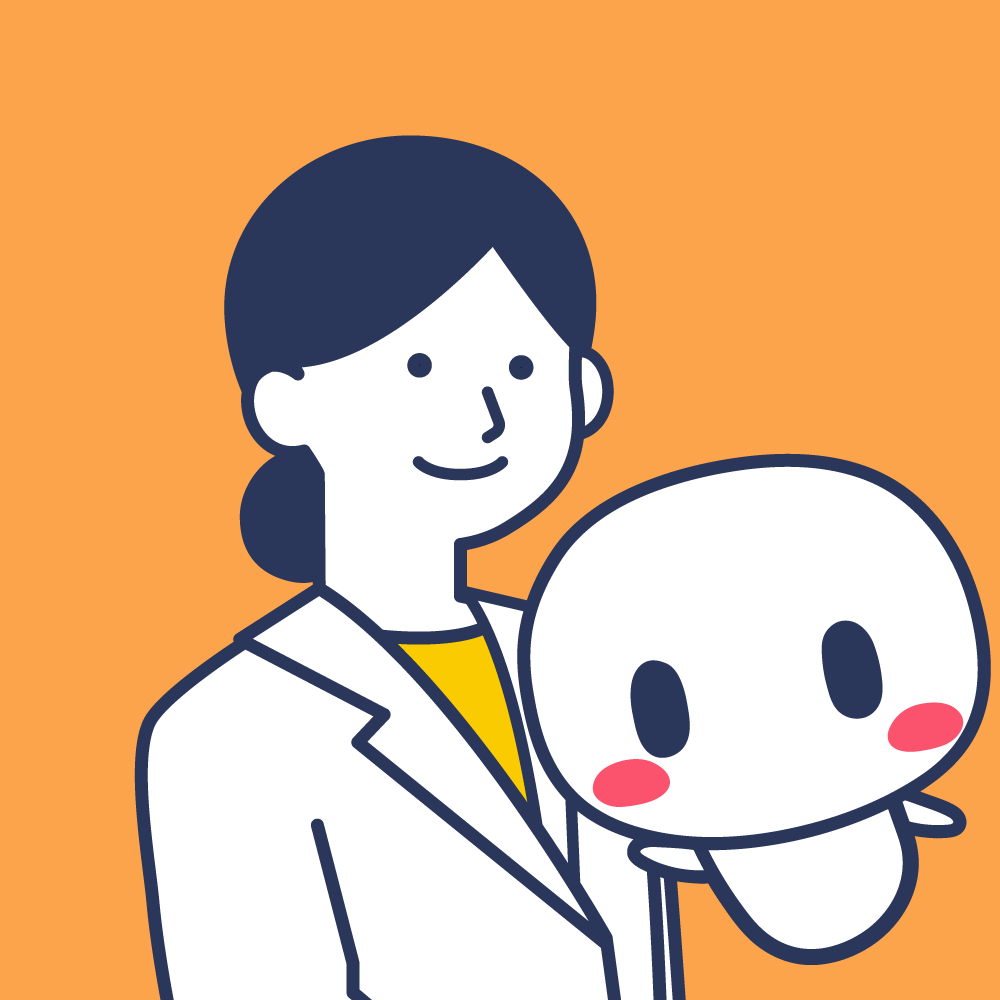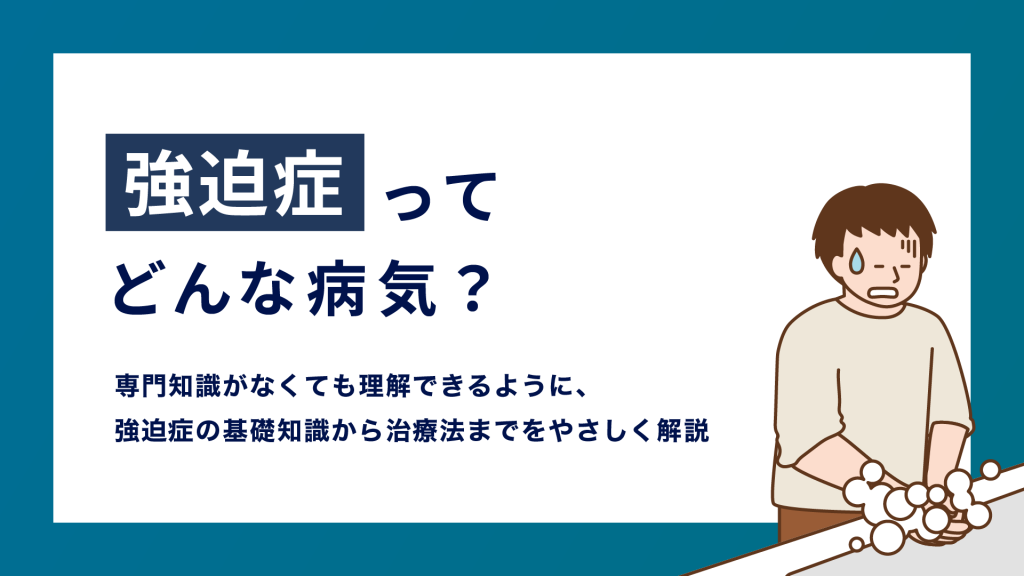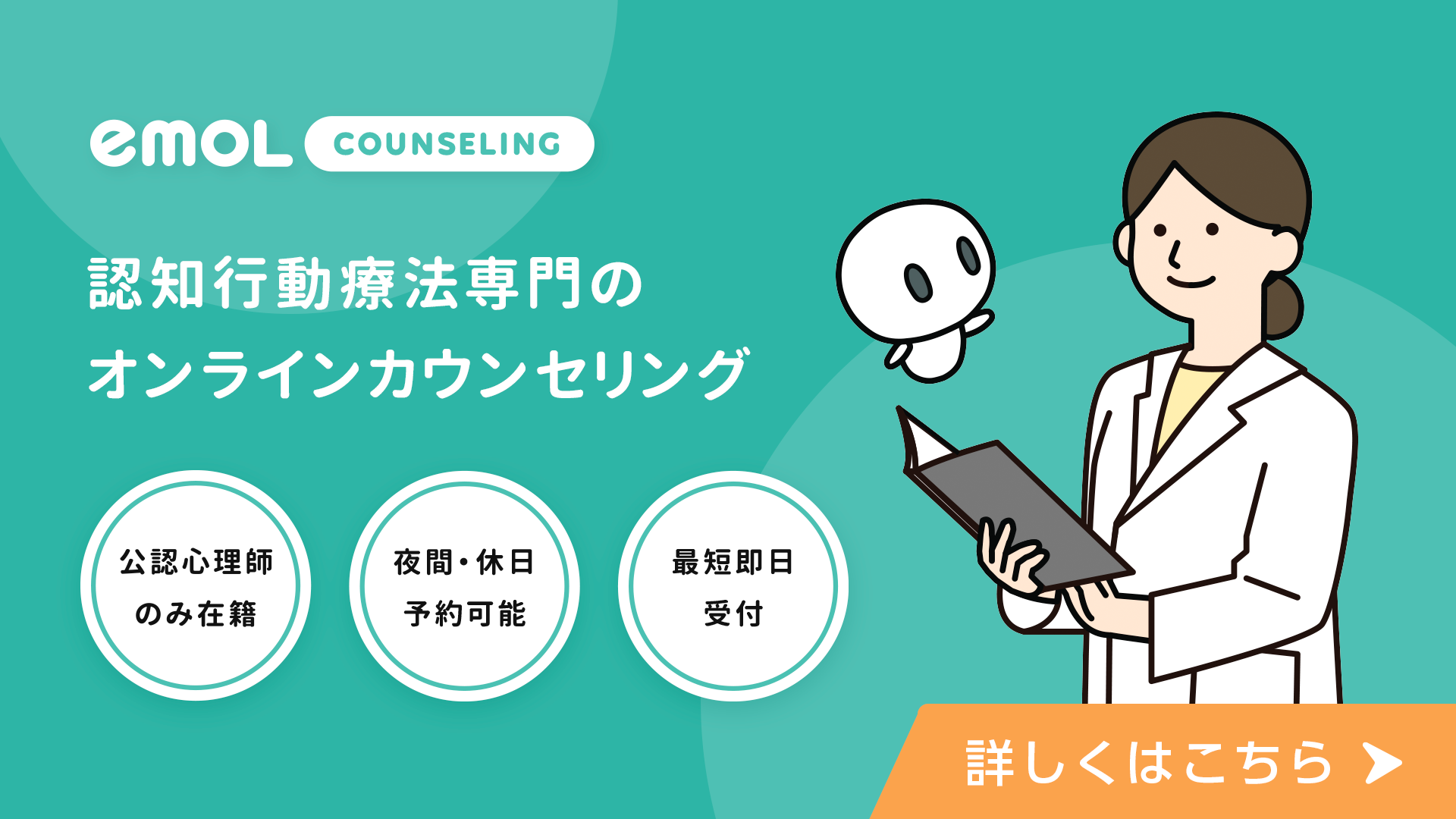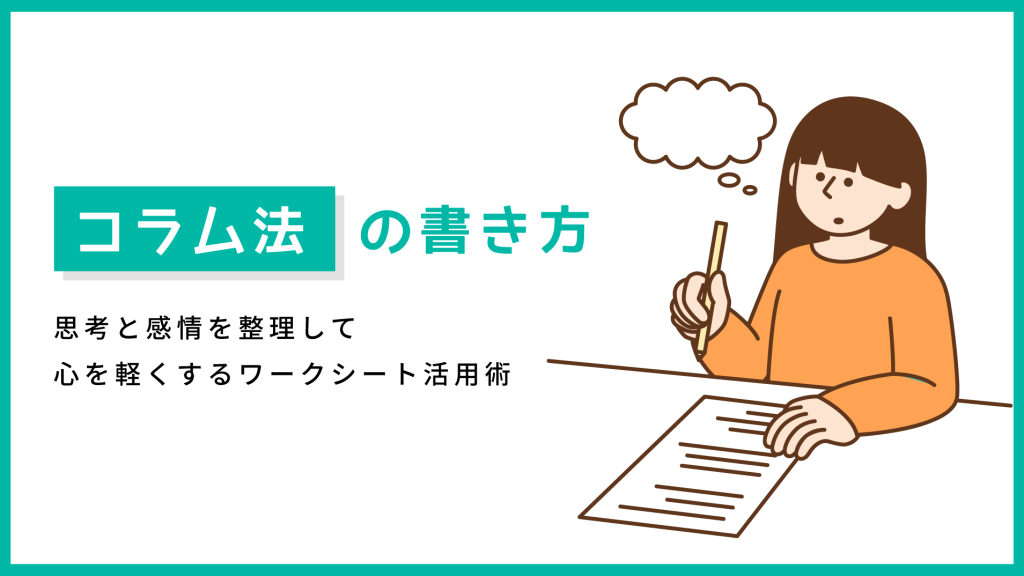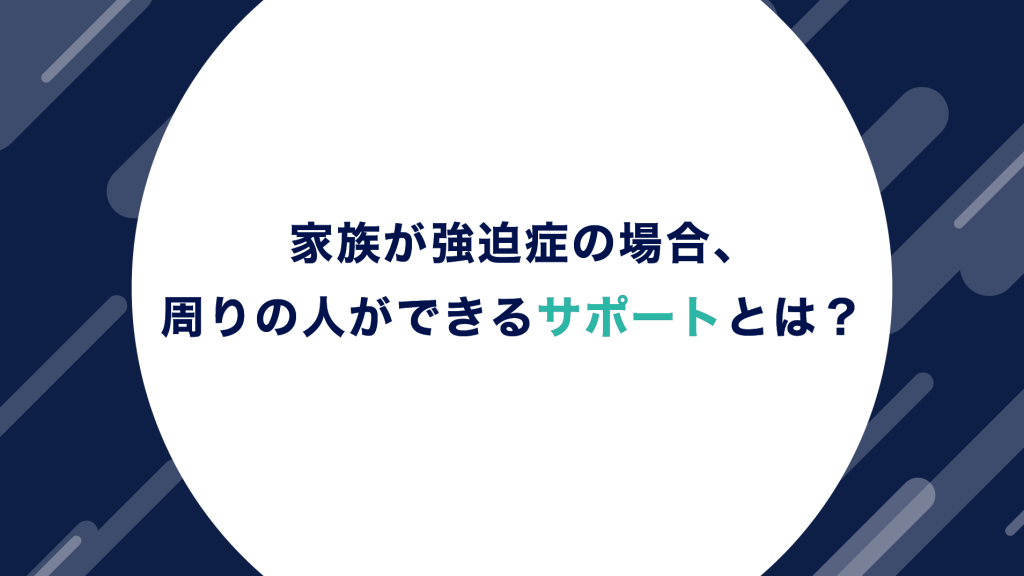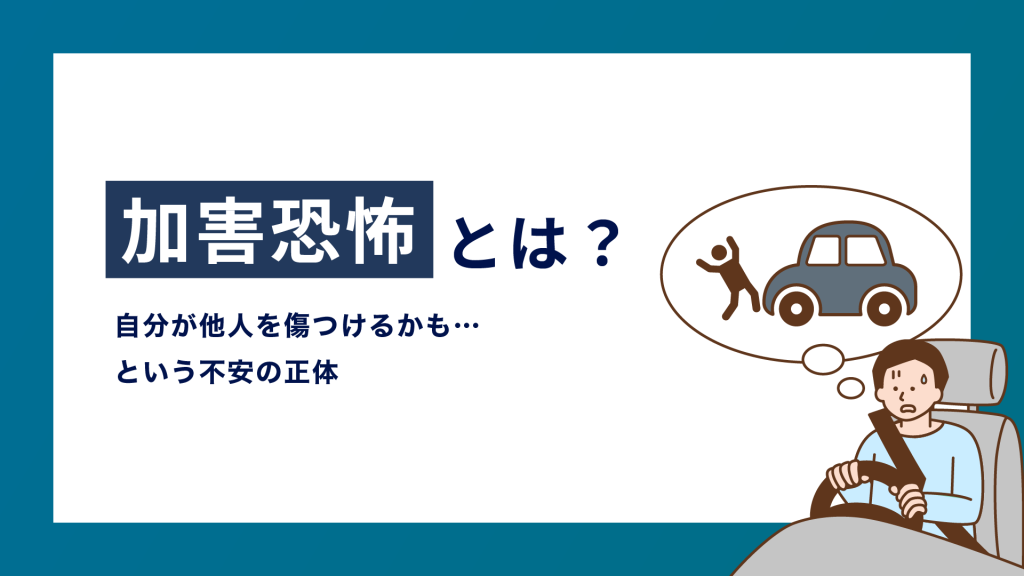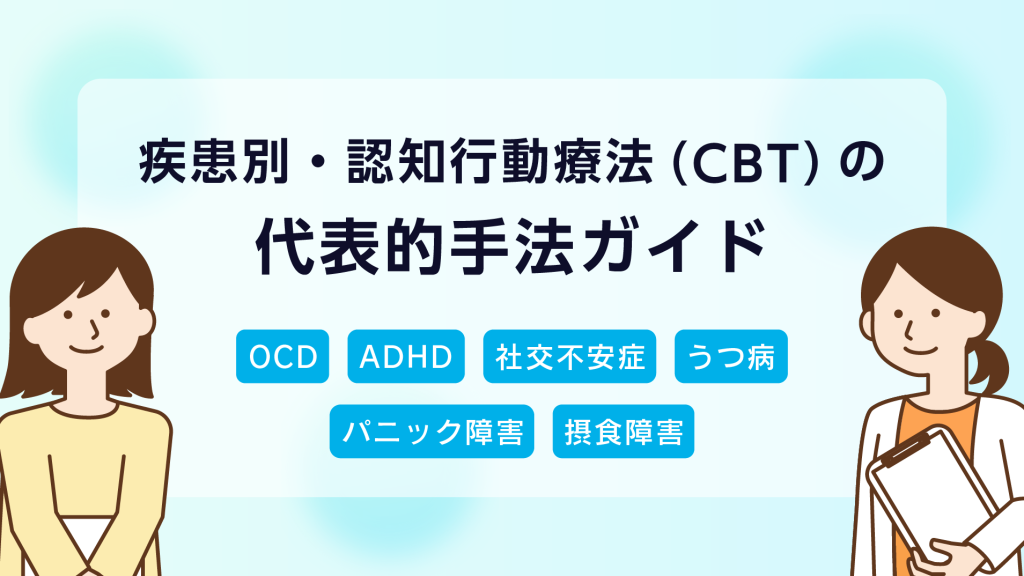「鍵を閉めたはずなのに心配で家へ戻った」「手を洗っても“まだ汚れている気がする”」。こうした“わかっているのにやめられない”思考や行動が続く病気が強迫症(強迫性障害/OCD)です。
世界的な調査では、一生のうち1〜3%程度の人が経験すると報告されています。症状は遅い小児期〜若年成人に始まることが多く、平均年齢は約19歳です。小児発症もありますが、40歳以降の初発は比較的まれです。放置すると勉強や仕事、家族関係に影響が出やすい反面、早く治療を始めれば大きく良くなる人はたくさんいます。
強迫症は、「強迫観念」と「強迫行為」という2つの特徴的な症状を中心に現れる心の病気です。名前は聞いたことがあっても、実際にどんな状態なのか、どのような治療があるのかを詳しく知っている人は少ないかもしれません。
この記事では、専門知識がなくても理解できるように、強迫症の基礎知識から治療法までをやさしく解説します。
目次
強迫症(強迫性障害)とは?
強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder, OCD)は、自分でも不合理だと分かっていながら、頭に浮かぶ考えや不安(強迫観念)にとらわれ、それを打ち消すための行動(強迫行為)を繰り返してしまう状態を指します。
脳の働き方の特徴や神経伝達物質の不均衡などが関わっていると考えられており、単なる「性格の問題」や「几帳面すぎるだけ」ではありません。
強迫症の2つの柱
強迫症は、「強迫観念」と「強迫行為」を中心とする病気です。
1. 強迫観念
頭に繰り返し浮かび、どうしても振り払えない考えやイメージ、不安を「強迫観念」と呼びます。
代表的なものは次の通りです。
- 確認型:「ガスの元栓を閉め忘れたのでは」「ドアを施錠したか不安」
- 洗浄・潔癖型:「手にばい菌がついている」「汚れているかも」
- 加害型:「自分が誰かを傷つけてしまうのでは」
- 縁起型:「特定の数字や順番を守らないと悪いことが起きる」
- しっくり型:「この配置や感覚が“しっくり”くるまでやり直したい」
2. 強迫行為
強迫観念による不安を打ち消すために繰り返してしまう行動です。
例としては:
- 何度もドアの鍵を確認する
- 手を1日に何十回も洗う
- 特定の儀式的な手順を繰り返す
- 数字を数え直す
- 何度もものを整列する
こうした行動は一時的に不安を和らげますが、長期的には強迫観念を強めてしまい、悪循環に陥ります。
どんな症状が出やすい?
| 頭に浮かぶ不安(強迫観念) | 安心を得る行動(強迫行為) |
| 汚れ・ばい菌が怖い | 手洗い・消毒を何度も行う |
| 火や鍵を閉め忘れた気がする | 戸締まりやガス栓を繰り返し確認 |
| 事故や犯罪をした気がする | 過去の行動を思い返して何度も確認 |
| 不吉な数字を避けたい | “縁起が悪い”数字を見えない位置に動かす |
| 物が左右対称でないと落ち着かない | 物をピシッと並べ直す |
| 冒涜的・攻撃的なイメージ | 決まった回数の祈りや言葉を唱える |
| 家族が病気になる映像が浮かぶ | 家族に「大丈夫?」と何度も尋ねる |
| 重要なメモを逃した気がする | メモ帳を書き直す・スクショを重ね撮り |
| 時間に遅れるのが極端に不安 | 時計を合わせ直し、アラームを複数設定 |
強迫症の原因
完全には解明されていませんが、複数の要因が組み合わさることで発症すると考えられています。
- 脳の働きの異常:セロトニンなどの神経伝達物質の不均衡
- 遺伝的要因:家族に強迫症の人がいると発症リスクが高まる
- 心理的要因:強い不安傾向や完璧主義
- 環境要因:ストレス、生活環境の変化、トラウマ体験
強迫症の人が直面する困りごと
強迫症の困難さは、日常生活に支障をきたすほど時間とエネルギーを奪われてしまうことです。以下に、よくある具体例を挙げます。
1. 時間がどんどん奪われる
- 鍵を閉めたか不安で10回以上見に行く → 出勤に毎朝1時間以上かかる
- 手を洗いすぎて、家事や勉強を始められない
2. 生活の自由が制限される
- 電車のドアがちゃんと閉まったか気になって下車できない
- 公共トイレや飲食店を避けるようになり、外出が減る
3. 身体的な影響
- 洗浄のしすぎで手が荒れてひび割れる
- 強い緊張や不安で疲れやすく、睡眠が浅くなる
4. 人間関係のトラブル
- 家族に「確認してほしい」と何度も頼んでしまう → 家族も疲弊し関係が悪化
- 「変に思われるのでは」と友人関係を避けるようになる
5. 「不完全さ」に苦しむ
- 「偶数でないと落ち着かない」ために、無意味に動作を繰り返す
- 書類の文字が「しっくりこない」と書き直しが止まらない
強迫症の治療法
強迫症は適切な治療で改善可能です。主な治療は以下の2つです。
1. 認知行動療法(CBT)
特に有効とされているのが、曝露反応妨害法(ERP: Exposure and Response Prevention)です。
これは、あえて不安を引き起こす状況に直面(曝露)し、「強迫行為をしない」練習を繰り返すことで、不安が徐々に減っていくことを体験的に学ぶ治療法です。
例:
- 「手が汚れたかもしれない」と思っても、手を洗わずにそのまま過ごす
- 「鍵を閉め忘れたかも」と感じても、確認に戻らない
最初は強い不安が生じますが、続けることで「行為をしなくても大丈夫」と学習でき、不安が弱まります。
2. 薬物療法
主に SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) が使われます。
これは脳内のセロトニンを調整し、強迫症状を軽減する効果があります。
薬物療法と認知行動療法を併用することで、より高い改善効果が得られるケースも多いです。
強迫症と「巻き込み」
強迫症では本人だけでなく、家族や身近な人を「巻き込む」行動がしばしば見られます。
巻き込みの例
- 「本当に手が汚れてないよね?」と何度も家族に確認する
- 「ガスの元栓を閉めたか一緒に見て」と頼む
- 「玄関のドアがちゃんと閉まったか確かめて」と強要する
一時的に安心できても、本人の不安はまた戻ってきます。さらに周囲も巻き込まれ、家族全員の生活が不自由になってしまうことがあります。
巻き込まれた家族の困りごと
- 何度も同じ質問に答えさせられて疲れる
- 本人を安心させるために確認作業を手伝わされる
- 「協力しないと怒られるのでは」と不安になり、家族関係が悪化する
悪循環
巻き込みに応じることで本人の不安は一時的に落ち着きますが、「不安→確認→安心→また不安」という悪循環を強めてしまいます。
家族が協力すること自体が、結果的に強迫行為を維持させる要因になってしまうのです。
「大丈夫だよ?」と何度も保証する・確認を代行するなどの巻き込みを少しずつ減らすことが大切です。これは曝露反応妨害法の学習を助け、長期的な改善につながります。
周囲ができるサポート
強迫症は「気合いでやめられるもの」ではありません。
家族や友人ができるサポートは:
- 無理にやめさせようとせず、安心できる環境を作る
- 「理解しよう」という姿勢を持つ
- 治療やカウンセリングへの受診を勧める
受診の目安
- 強迫行為に1日1時間以上かかる
- 学業・仕事に支障が出ている
- 家族関係に摩擦が生じている
- 強い苦痛を感じている
このような場合は、精神科・心療内科での相談をおすすめします。
まとめ
強迫症(強迫性障害)は、強迫観念と強迫行為の悪循環で日常に大きな影響を及ぼす病気です。
困りごとには、時間や生活の制限、身体的負担、人間関係の悪化、そして家族や周囲を巻き込んでしまうことがあります。しかし、認知行動療法(曝露反応妨害法)や薬物療法で改善が可能です。
「巻き込み」も含め、家族全体で病気を理解し、適切な支援を受けることが回復への大切なステップになります。
強迫症について知るアプリ『フアシル-O 強迫を乗り越えよう』
強迫症について知るアプリ『フアシル-O』は、兵庫医科大学精神科神経科学との共同研究にて開発したアプリです。
推奨用途:強迫症の患者、その家族、強迫症の一歩手前の未病者の方への疾患理解の促進
iOSアプリダウンロード:https://bit.ly/fuasil_o_app
Androidアプリダウンロード:https://bit.ly/fuasil_o_google
※当アプリは診断や治療など医療行為・医療類似行為ではなく、疾患について知ることを目的としています。疾患の診断・治療をご希望の方は、医師の診断および治療をお受けください。

【参考】
- 厚生労働省. 「強迫症に対する認知行動療法マニュアル」. 精神・神経疾患研究開発費事業.
- 日本精神神経学会. 精神疾患の診断・治療ガイドライン(強迫症/OCD).
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). 2013.
- National Institute of Mental Health (NIMH). Obsessive-Compulsive Disorder.
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd - Ruscio AM, et al. The epidemiology of obsessive–compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. Mol Psychiatry. 2010;15(1):53-63.
- International OCD Foundation (IOCDF). About OCD and Treatment: Exposure and Response Prevention (ERP).
https://iocdf.org/about-ocd/ocd-treatment/erp/ - Merck Manuals. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).
https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/obsessive-compulsive-and-related-disorders/obsessive-compulsive-disorder-ocd - Lebowitz ER, et al. Family accommodation in obsessive–compulsive disorder. Expert Rev Neurother. 2014;14(3):229-237. (巻き込みに関する代表的研究)