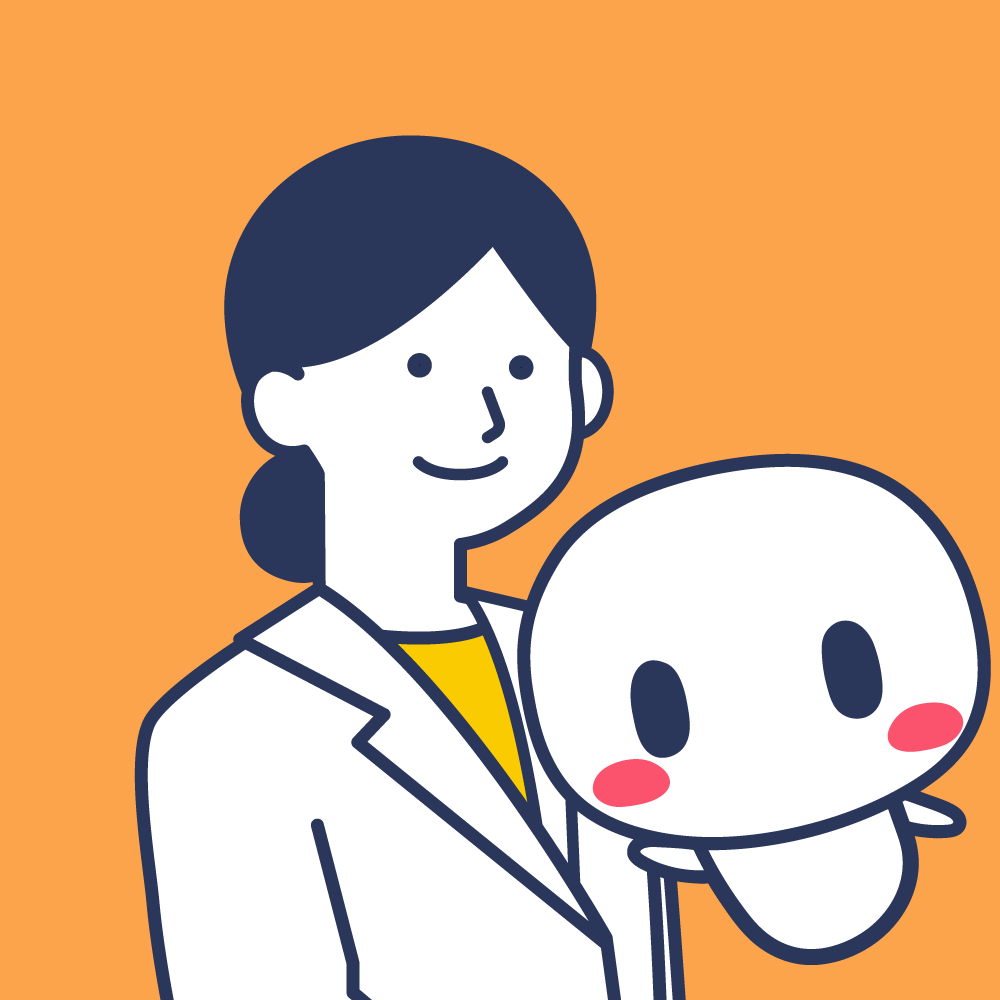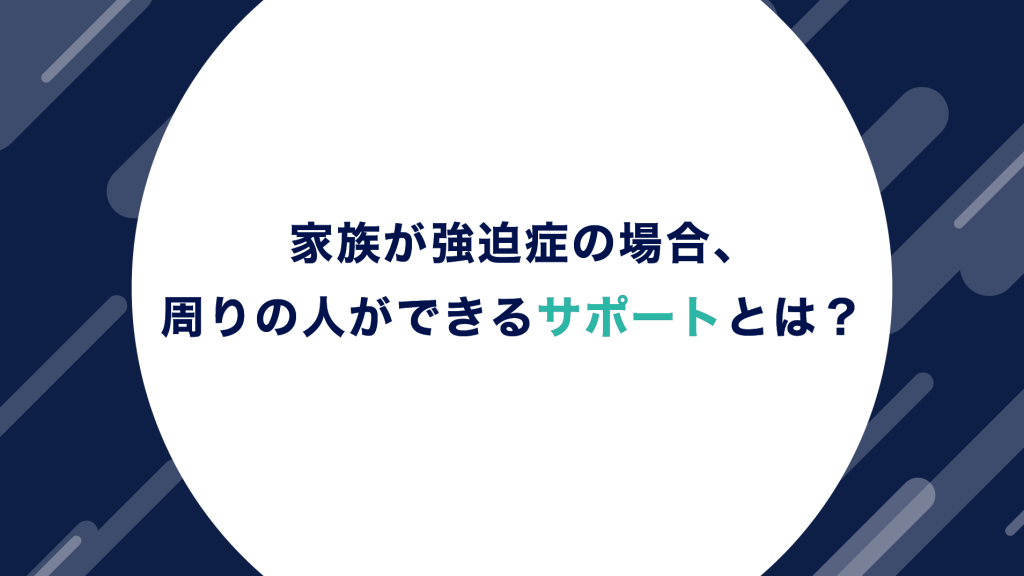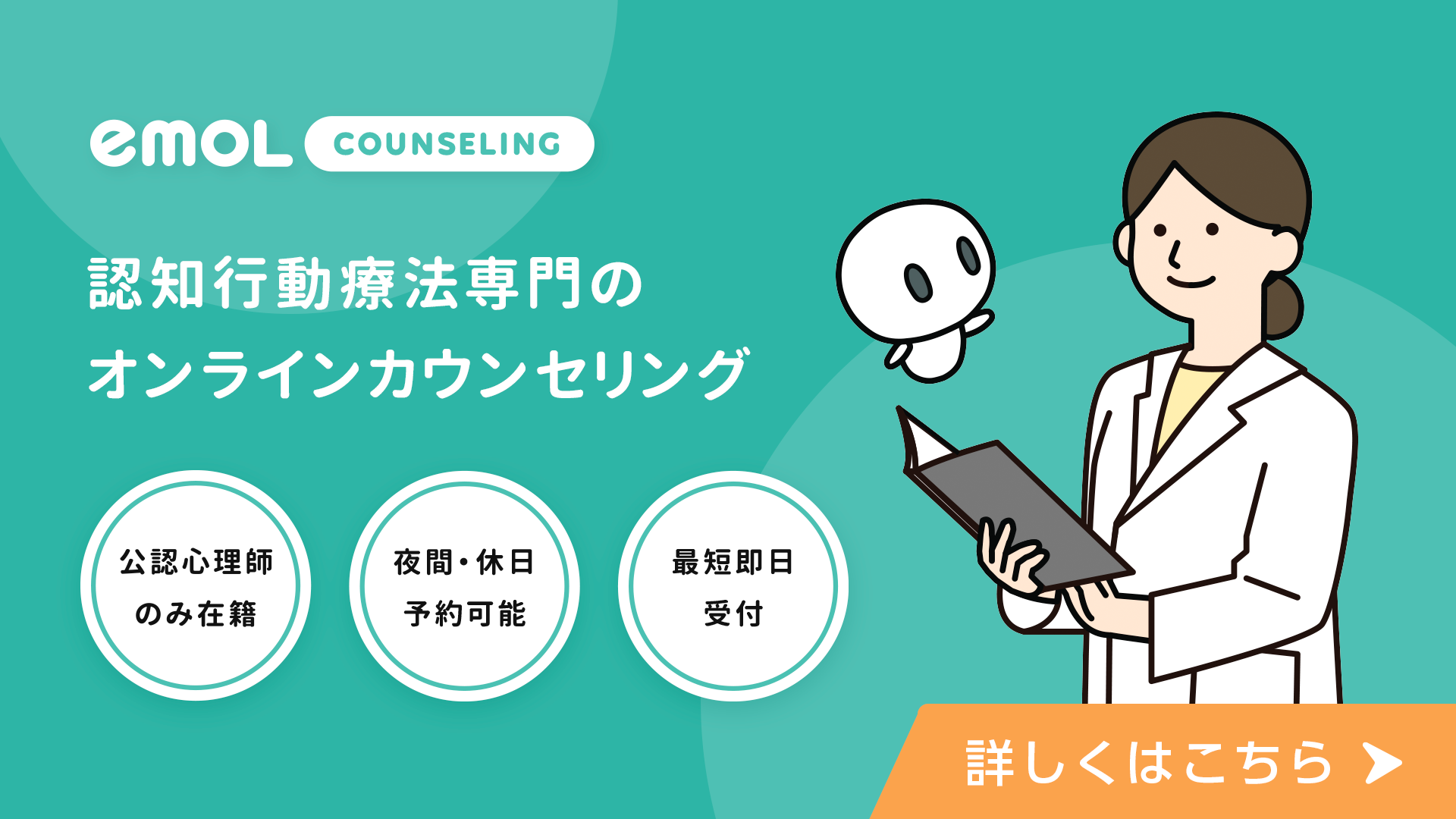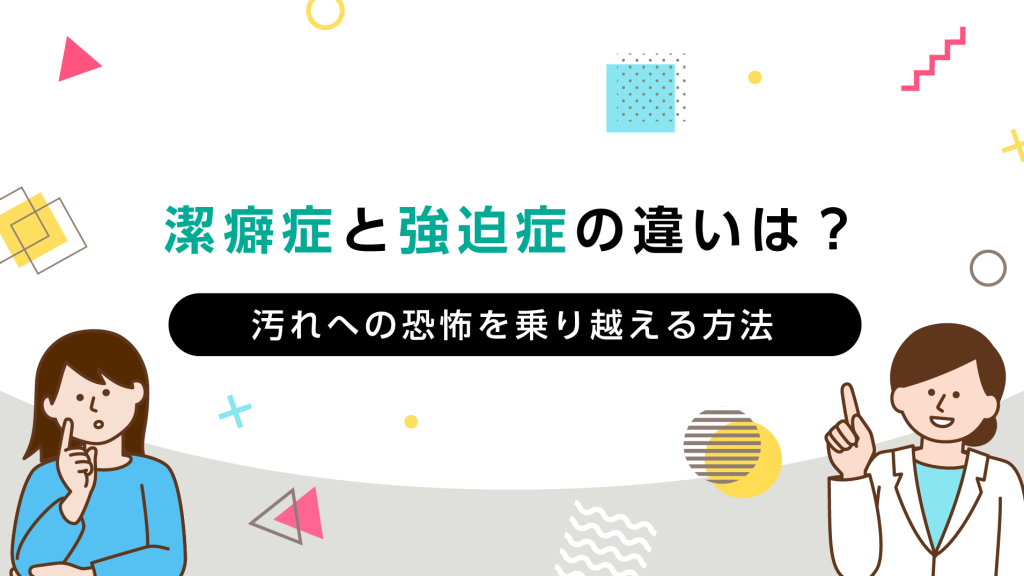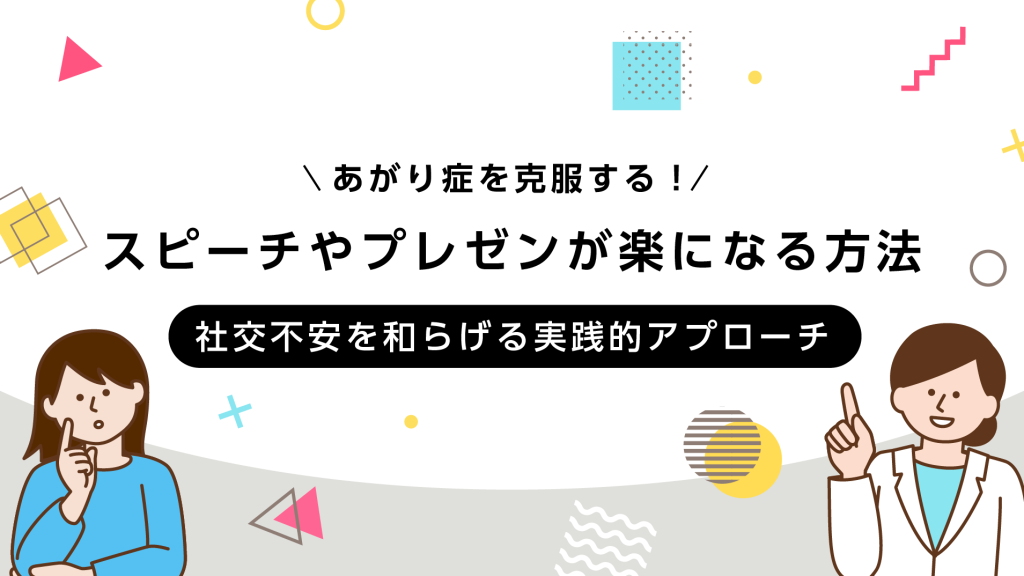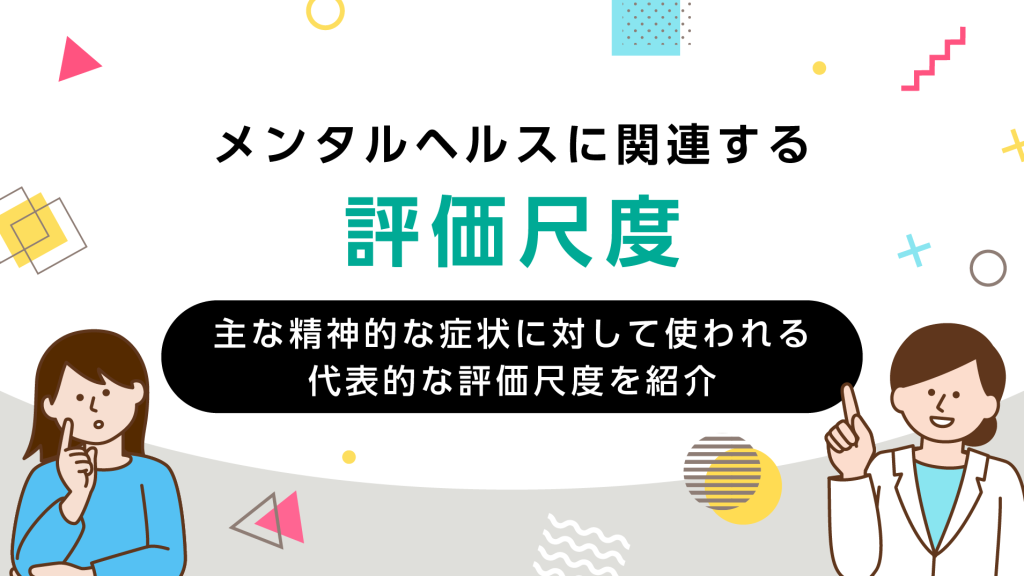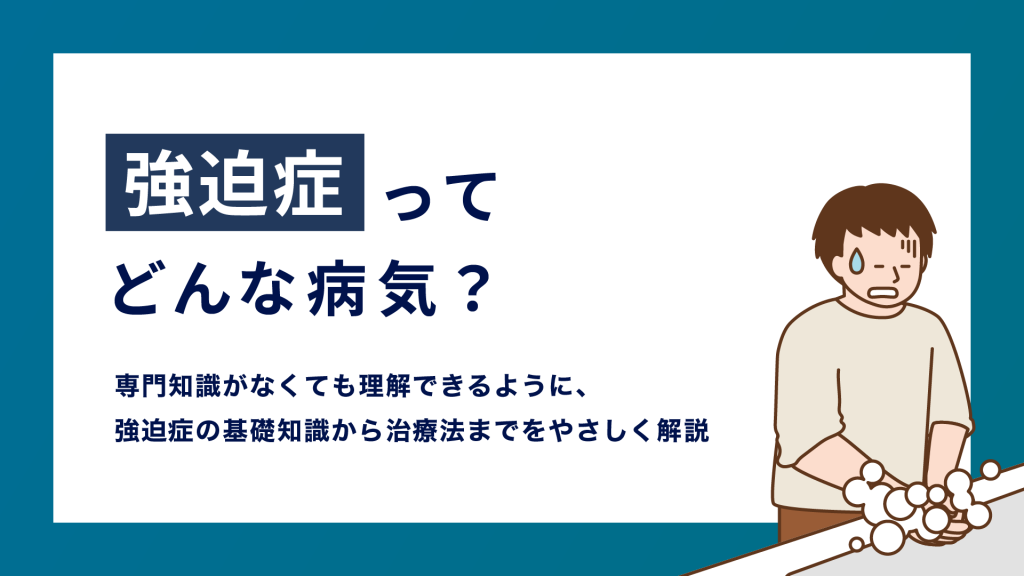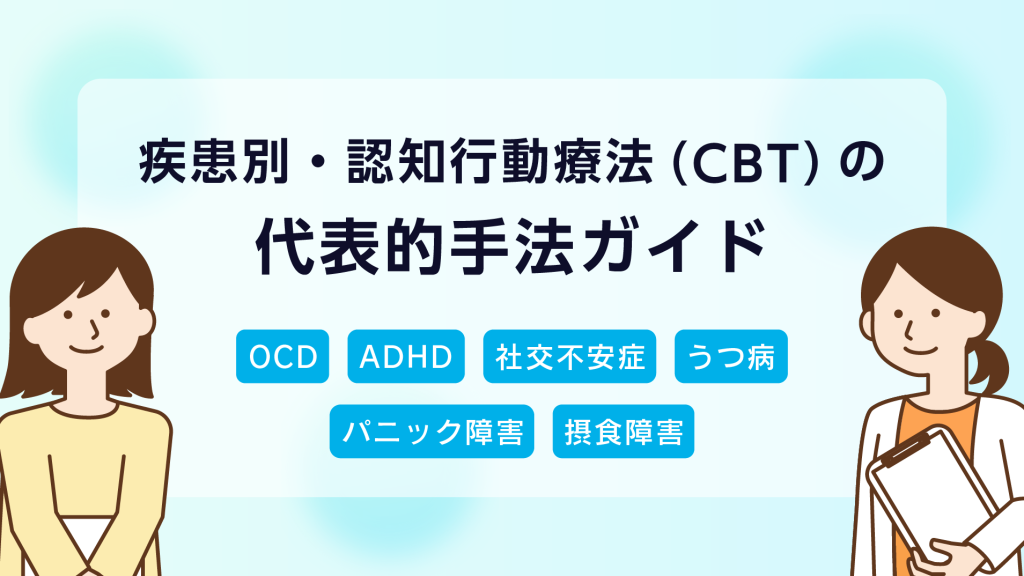「家族が手を何度も洗い続けている」
「ドアの鍵を繰り返し確認して出かけられない」
「同じ質問を何度もされ、答えても不安が消えない」
このような行動を繰り返すのは、強迫症(強迫性障害:OCD)の症状かもしれません。
強迫症は、本人だけでなく、家族や周囲の人にも大きな影響を与える病気です。
家族として「どうサポートすればいいのか」「何を言えば逆効果なのか」と悩む方も多いでしょう。
この記事では、強迫症の基礎知識と、家族や周囲ができる適切なサポート方法についてわかりやすく解説します。
目次
強迫症(強迫性障害)とは?
強迫症とは、「強迫観念」と「強迫行為」を特徴とする精神疾患です。
- 強迫観念:不安や恐怖を伴う繰り返しの考えやイメージ
(例:「手に汚れやばい菌がついて大変なことになるかも」) - 強迫行為:不安を打ち消すために繰り返す行動や心の中の儀式
(例:手洗いを何度も繰り返す、ドアの鍵を確認し続ける)
本人も「やりすぎだ」とわかっていても、不安に耐えられずやめられないのが特徴です。
そのため、日常生活や学校、仕事に大きな支障をきたすことがあります。
強迫症が家族に与える影響
強迫症は本人の苦しみに加えて、家族にも次のような負担をもたらします。
- 出かける準備に時間がかかり、一緒に行動できない
- 「大丈夫だよ」と何度も答えさせられる
- 本人が避ける行動(電車に乗れない、外出を拒む)に合わせざるを得ない
- 家族自身が疲れやイライラを感じる
このように、家族が強迫症の症状に巻き込まれることを「家族巻き込み」と呼び、症状を悪化させる要因になることもあります。
家族ができるサポートの基本
1. 否定せずに理解を示す
強迫症の症状を「気にしすぎ」「考えすぎ」と否定するのは逆効果です。
本人にとっては現実的で強烈な不安だからこそ行動を繰り返しています。
「あなたが不安に感じていることは理解しているよ」と共感を示すことが大切です。
2. 強迫行為に協力しすぎない
本人から「何度も確認してほしい」と求められることがあります。
家族が答え続けると一時的には安心しますが、結果的に強迫行為を強化してしまうことになります。
例:
- 「ドア閉めた?」と毎回聞かれて答える → 安心感は一時的
- しかし次も同じ不安が出て確認が必要になる
協力しすぎず、少しずつ「本人が不安を乗り越える練習」を支える姿勢が重要です。
3. 安心させようとしすぎない
「大丈夫だから」「そんなこと起きないよ」と繰り返すのも効果が薄い場合があります。
強迫症の不安は「理屈」ではなく「感覚」として生じるため、言葉だけで解決できません。
むしろ「また確認しなければ」と強迫行為を強めてしまうことがあります。
4. 専門的な治療につなげる
強迫症は治療によって改善が可能な病気です。
特に効果的なのは以下の方法です。
- 認知行動療法(CBT):不安に向き合い、強迫行為を減らす練習を行う
- 曝露反応妨害法(ERP):あえて不安を感じる状況に直面し、確認や儀式を我慢する体験を積む
- 薬物療法(SSRIなど):脳の神経伝達物質の働きを整える
家族は、本人が治療を受けやすいようにサポートし、受診のきっかけを作ることが大切です。
5. 家族自身のケアも大切にする
家族が疲れ切ってしまうと、本人を支える余裕がなくなります。
そのために:
- 信頼できる人や支援機関に相談する
- カウンセリングを家族も利用する
- 趣味や休養の時間を確保する
「支える人自身の心の健康」も忘れないことが重要です。
家族がやってはいけないこと
サポートのつもりが逆効果になる行動もあります。
- 強迫行為を完全に禁止する
- イライラして「やめろ!」と怒鳴る
- 本人の行為に巻き込まれすぎる
- 不安を軽く扱い「そんなこと気にするな」と突き放す
これらは本人の不安を増大させ、家族関係を悪化させる原因になります。
サポートの具体例
- 「確認したい気持ちはわかるよ」と受け止める
- 「でも一緒に1回だけでやめてみようか」と提案する
- 「今日は5回じゃなくて3回にしてみよう」と小さな目標を設定する
専門家の指導に基づいて、少しずつ強迫行為を減らす練習をサポートする
専門機関や支援団体を利用する
強迫症は一人で抱える病気ではありません。
日本には、精神科・心療内科のほか、家族向けの相談窓口や支援団体もあります。
- 精神保健福祉センター
- 自治体のメンタルヘルス相談窓口
- OCD(強迫症)に特化したサポート団体
こうした機関を活用することで、本人も家族も安心して治療に取り組めます。
まとめ
家族が強迫症の場合、周囲ができるサポートは「否定せずに理解を示すこと」「強迫行為に巻き込まれすぎないこと」「専門的な治療につなげること」が基本です。
- 強迫症は「やめたいのにやめられない病気」
- 家族の対応が、症状の悪化にも回復にも影響する
- 家族自身もケアを忘れず、専門機関や支援を活用する
本人が安心して治療に取り組めるように、家族が適切なサポートを行うことが回復の第一歩になります。
強迫症について知るアプリ『フアシル-O 強迫を乗り越えよう』
強迫症について知るアプリ『フアシル-O』は、兵庫医科大学精神科神経科学との共同研究にて開発したアプリです。
推奨用途:強迫症の患者、その家族、強迫症の一歩手前の未病者の方への疾患理解の促進
iOSアプリダウンロード:https://bit.ly/fuasil_o_app
Androidアプリダウンロード:https://bit.ly/fuasil_o_google
※当アプリは診断や治療など医療行為・医療類似行為ではなく、疾患について知ることを目的としています。疾患の診断・治療をご希望の方は、医師の診断および治療をお受けください。

参考文献一覧
- 厚生労働省. 「みんなのメンタルヘルス総合サイト 強迫症」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/nation/info_07.html - 国立精神・神経医療研究センター. 「強迫症」疾患ナビゲーション
https://www.ncnp.go.jp/nimh/clinical/ocd/ - 日本うつ病学会. 「強迫症の診断・治療ガイドライン」
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). 2013.
- Mayo Clinic. “Obsessive-compulsive disorder (OCD).”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ocd/